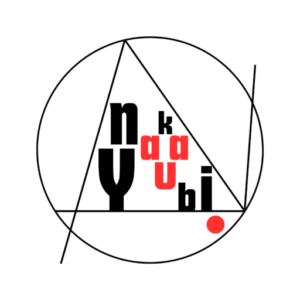【戯曲を読む】No.14 松原俊太郎『山山』 発表/初演:2018年
話の流れ
妻は山を登っている。夫は妻を愛している。夫は山で働いている。(クリックで詳細)
「別の場所から自分と自分のいる場所を見つめたい」がためにアメリカに行こうとする娘と、そして家に帰ろうとする放蕩息子。娘のアメリカ行きを恋人の社員はを好ましく思っていない。娘の恋人と夫(=娘の父)は仲が悪く、とっくみ合う。娘はそれをみて、二人の愛のわずらわしさ(父の愛のほうが複雑)、しつこさが「ほんと嫌」という。
観光にきたカップルは、社員から以下のような説明を受ける。美しい山が、汚染されたもう一つの山に侵食されている。伝染を防ぐために、除染作業を行う労働者たちは精を出して働いてくれている。労働者のなかには、作業員だけでなく、ブッシュというアメリカ製のロボットもいる。 夫は、家族とともにピクニックに行く予定だったが、体の汚れが許容量を超えたため、隔離され連れ去られてしまう。夫のいないピクニックで、悲しむ妻を心配して、娘はアメリカ行きをやめると、ついに帰ってきたばかりの放蕩息子の弟に言う。急に夫が帰ってくる。夫「終わらせやしないさ、だらだらとでもいい、つづけよう、一つとして同じ時間などないのだから、そのつづいているなかにいつもとは違うものがまぎれ込んでいるのだから、それを見つけて、またつづけよう」。
松原俊太郎(1988-)
熊本県出身。神戸大学経済学部卒。2014年春、地点による『ファッツァー』(ベルトルト・ブレヒト作、三浦基演出)に魅せられ、戯曲を書き始める。戯曲『みちゆき』で第十五回AAF戯曲賞大賞受賞。そのほかの戯曲に『忘れる日本人』『正面に気をつけろ』、小説に『またのために』。
ノート――つもらない話
本作は、日本に暮す多くの人々にとってたいへんアクチュアルな問題をかなり直接的に材料にしたものである。戯曲を上演すること自体が、過去の、古びた制度と看做されつつある。膨張する現代を対象にして、強度を保ちながら最後まで耐久可能な戯曲があるとしたら、それはどんな形式になるだろうか。そう思い悩んでいる多くの日本の劇作家たちにとって、本作は一つの希望と言える。だが、どんな場所で、どんな出会いがあって本作が生まれたかということを知ると、嫉妬し絶望するかもしれない。経緯については最近のことであるし、そのあたりのことは何十年、何百年後の学者たちに任せ、脇に措き、もっと広い文脈や、もっと細かい文体に目を向けてむけてみよう。本作は、アクチュアルな問題を無理に文学的な形式へ落とし込もうとしていない。だから、死んだ演劇、上演の化石に堕落しておらず、ことばは生き生きとしている。そして本作は取り扱おうとしている問題が問題としてそのままの姿で書かれた、リアルな作品である。
この戯曲が発表される二十年前、第42回の岸田國士戯曲賞の講評で別役実が現代劇についてこう指摘している。「現代劇は書き難くなっている。それは第一に、情報としての世界が広がり、状況が重複しあい、ひとつのドラマが他と相殺されがちで無化する傾向にあること、さらには、ドラマの形造るべき対人間関係が、地域共同体、家族共同体の崩壊により、構造として確かめ難くなったこと、などによるものと考えていいだろう」(別役実「重層化された風景」白水社、1998年)。手に余る量の情報に囲まれて、現代人は生きている。手のひらのうえに乗っているはずのスマートフォンから提供される情報ですら、私たちが一日に処理できる量を凌駕する。例えば、中学時代の友人の状況など、相当仲良くない限りは一生わからないままのはずった。ある日突然再会し、「結婚して、もう子どもが二人? あんなだったお前がなあ」と感慨に耽り、「つもる話もあるから、一杯どうだ?」・・・・・・という人生のささやかなワンシーンは、例えばフェイスブックによってかなり消滅しただろう。別役が第一に指摘する問題は、それだけでは演劇になりそうにはないが、そのもととなっている小さな体験というドラマの消滅であり、それは現在も深刻化している。
技術によって生活が規定されるようになったのは産業革命からであるが、技術によって生活が操作されるようになったのは、20世紀以降であろう。そして、今や個人の生活レヴェルにおいて、人びとは一生かけても扱いきれないほどの情報量と対峙するようになった。そして、国家レヴェルでも同じことが起きる。核兵器、原子力爆弾、そして原子力発電の登場である。これにより、鈴木成高の言を借りれば、「兵器を兵器によって防衛することができない」すなわち「戦争を戦争によって防衛することができな」い時代が到来した。そして原発事故は日本人が、日本という国家が「扱いきれない」技術を扱おうとしていたことを自覚させるものだった。この事故は、同じ形姿の問題を、個人と国家のそれぞれのレヴェルで同時に突き付けたのである。原爆から原発に要約される日本の20世紀の議論については、戯曲を思考する範疇を超えてしまうので、また脇に措こう。
本作ではその最前線に立たされた人々が、何もかも押し流す、膨大な物量を目の当たりにする。それは可視化された情報である。私は、バブル崩壊前の、80年代の一部の演劇を「物量演劇」と呼んでいた。しかし、本作とそれらとは根本的に異なる。かつての物量演劇にはなかった、物量への自覚と不条理が本作には書き込まれている。さらに、破綻しかけている、はちきれんばかりの分厚いセリフが、物量と見なされるもののうちの多くを占めていることも過去の物量演劇との大きな違いである。それは製造業から情報産業へ世界の重要産業が移り変わったことを示している。
「ムーアの法則」によれば、プロセッサチップの処理速度は1.5年ごとに倍増するという。このまま、私たちを取り囲む情報量が増え続けるとしたら「山山」はもはや山以上のものになってしまうだろう。「山」が人間が一度に認識できるもののなかで、最も大きなものであるとするなら、それを超える見込みのある将来に行き詰まりを感じてしまいそうになる。大きな世界を捉えることを諦めて、等身大の世界に籠ってしまう者も出るだろう。それでも、演劇から大きな世界を見せあるいは映し、表現する可能性は、現代にまだ残されているだろうか。
また、作者の文体の特徴は、谷崎潤一郎のそれと類似することも指摘しておかなければならない。谷崎は『文章読本』において、源氏物語派の、「水の流れるやうな、何處にも凝滞することのない調子」で「センテンスの切れ目がない、全体の一つの連鎖したもの」こそ、最も日本文の特長を発揮した文体であると言い、『春琴抄』ではっきりとこの主張を実践し、『細雪』では磨きをかけた。
もちろん、作者が生きる日本語と谷崎が生きた日本語は大きく異なり、劇作をあまりしなくなり、小説家に軸足を置いた谷崎と「純粋劇作家」ともてはやされる作者を同列に語ることには、かなりの抵抗があるかもしれない。それでも、小生は谷崎の主張に与みし、その系譜に作者を連ね、願わくばそこに岡田利規を加えたいとさえ云いたい。大正末から昭和にかけて書かれたプロレタリア演劇の強い政治性を帯びた文体と、先の谷崎が主張した「最も日本文の特長を発揮した」流麗な文体というかけ離れているように見える二つが、本作において統合されている。佐々木敦が言う「日本の演劇がもっともアクチュアルにポリティカルだった時代」、「「現代詩」ともっとも接近した時代」というのも一つの視点ではあるが、無闇に「詩」を形容詞として使う相手は、あの若い政治家に限るべきであり、本作や作者の理解においては、言語としての日本語の特性という見地からの批評も必要である。