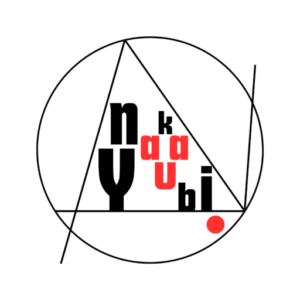【戯曲を読む】No.13 宮沢章夫『14歳の国』1998年初演
あらすじ
ある中学校の教室のように見えるが、それはごく抽象的なもので、そうとも見えるが、そうでないようにも感じる。(クリックで詳細)
ト書きにはアルファベットが付された机の配置が示されている。全二場。各50分。体育の授業中、生徒たちの制服や私物、勉強道具が机にある。そこへ、教師1、2、3が現れ、机の上のものを手にする。抜打ちの持ち物検査をしにきたのである。しかし、教師たちは、生徒に生徒らしい服装があるように教師にも教師らしい格好があるだとか、インディーズが何かだとか、美術部には一年生が何人いるのかなどといった他愛のない会話を繰り返すばかりで、持ち物検査の成果が上がらない。教師5はしきりに教室で煙草を吸おうとしては、別の教師に止められる。ある生徒の持ち物から「自分史」ノートが見つかるが、少し読むくらいで時間がなくなる。ノートを鞄にしまう。不意に暗転。第二場。一場から一週間後の同じ教室。やはり体育の授業中、また持ち物検査に入っている教師たち。花瓶が割れている。Lの鞄から出した紙片に刑法第四十一条、十四歳に未たざる者の行為は、これを罰せず」と書いてあった。そして一場ではなかった要注意のものが見つかりはじめる。机に刻まれたSATAKE SHINE(=サタケ(=教師2)死ね)という文字、デートクラブの番号、家族の顔に傷がつけられた写真。そして教師5が「望まれた」ナイフを見つける。しかしそれが誰の机から出たか教師5は明らかにしない。またやはり教師5は煙草を吸おうとする。一人の教師があの「自分史」ノートの一部を声に出して読む。「今週、ぼくは誕生日を迎えた。ぼくは、十五歳になった」。不意に暗転。暗がりの中に、あのピアノ曲が流れる。
宮沢章夫(1956-2022)
多摩美術大学中退。80年代半ば、竹中直人、いとうせいこうらとともに「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」を開始。90年より「遊園地再生事業団」の活動をはじめ、第二回公演『ヒネミ』で岸田國士戯曲賞を受賞。
ノート
三島由紀夫『サド侯爵夫人』、柳美里『魚の祭』などでも取られた、主人公=主題(に見えるもの)を隠す手法の一つといえる。「理解しえない」行為をする子どもたちを理解するためにとりあえず名付けることは繰り返し行われてきた。昔なら、「〇〇族」とかで、今は「ゆとり世代」とか「Z世代」とかでまとめる。これは、メディアにとっては便利な手法である。とにかく名付けることで、理解しえない現象を、理解できた気分になるので、人間は不安から解消される。
三島と柳の場合は、個人が隠されたが、本作では〈世代〉が隠される。行動原理、ここでは「欲しいもの」、欲望の根源にあるものを見えなくすることで、多種多様なる観客と「共同幻想」を共有する。三島の場合は「サド侯爵」、柳の場合は「冬逢」と個人であった。人物画や写真は、その人自身ではない。それはむしろその人自身ではないからこそ作品たりえる。そうであれば、当たり前のことかもしれないが、その対象は人物でなくてもいい。風景でも、感情でも、社会でもかまわない。そして、この考えを演劇に持ち込めば、そのもの自身ではないものしか表現できないこと=演劇の限界が、「演劇の可能性」に変化する。そして「それがそれ自身でないこと」によって、作者の視点つまり批評性が入り込む。本作の場合は、教師たちのありようが批評性として、主題に無理なく関わっている。だから、無意味に思える会話も観客にとって何かを想起させる。むしろ無意味でなくては、かえって一つの意味に限定されてしまい、観客の自由を制限してしまうことになるだろう。「実在しないもの」を題材にするための手法で描かれた戯曲である。