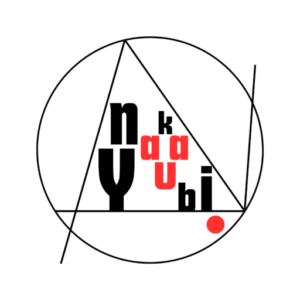【戯曲を読む】No.18 『桜の園』の „Pause“:アントン・チェーホフ『桜の園』はどのように演出/解釈されてきたのか
人間座第70回公演『桜の園』(2025/12/6-7)京都府立文芸会館
神田真直予約ページ: https://ticket.corich.jp/apply/384810/014/
回り道
学生劇団の美徳とは「いい加減さを許容すること」に尽きる。あるいは、80年代以降は「いい加減さを許容すること」が日本のカルチャー全体で重要になっていったような気がする。井上ひさしの戯曲には、まだ文学があるが、第三世代に入ってくると、彼等の戯曲は活字であるにもかかわらず、誰かが殴り書いたポエム崩れを読んでいるような気分になる。80年代からバブルにかけては、やはり大量生産・大量消費の「物量演劇」あるいは「浪費演劇」の時代だったのだろう。
震災はすでに起きたあとだったが、2010年代の中ごろ、そんないい加減な学生劇団にいた私でも、チェーホフは知っていた。しかし名前だけである。京都の学生であったにもかかわらず、劇団地点のチェーホフ上演も観ていない。最初から最後まで読んだこともないのに、自作の戯曲で『三人姉妹』などを引用していた。何も知らない、というのはほんとうに幸福なことだったと振り返って思う。結局、チェーホフ上演を観たのは、2024年10月20日、ベルリン、シャウビューネ劇場の『かもめ』(Die Möve, Regie: Thomas Ostermeier)がはじめてであった。
はじめてちゃんとチェーホフについて「考えた」のは、2019年のことである。利賀演劇人コンクール2019に応募することにした。書類審査があり、次に上演審査、そして最終上演審査という流れのなかで、書類審査の内容は、「最終上演審査のために、チェーホフから一つ、戯曲を選び、その演出プランを書け」というものだった。
学生も、学生劇団も卒業してしまった私は、とりあえず次のステップとしてこのコンクールをはじめ賞レースにあちこち参加することを選んだ。チェーホフなんか知っているだけで、ほとんど読んだこともないので、内容の発表があってからひとまず手に取った。しかし、作・演出ばかりやってきて、こういう古典戯曲を読み慣れていない私は、戯曲を読んで、その演出プランを考え、書類にするということができない。イプセン、シェイクスピアの上演も観たことがなかった。そこで、外枠から入っていくというか、背景から見ていくことにした。それ自体に時間をかけてしまい、『桜の園』本編を読み込むことは結局、今回の機会にいたる(2024年末ごろ)までなかった。
こういうとき、例えば
①「当時のロシアの生活史・文化史」
②「チェーホフの生涯と作品史」
③「チェーホフ戯曲の解釈史」
④「チェーホフ戯曲の演出史」
といったふうに資料を分類しておかなければ、情報の海に飲み込まれ、混乱してしまうことになる。そして、すべてが論理的につながっているわけでもなく、どうしても埋まらないピースが出てきたりすることもある。また、チェーホフの書いていることが「正しく現実を反映している」とも限らない。そういうときにうまく跳躍する必要が出てくる。なお、今回の資料集めは、やや「演出史」に偏ってしまったような気がしている。
そうして、できる限りの材料を揃えたうえでも、結局またセリフの解釈のために調べ物をする羽目になる。例えば以下のようなふとした一言も、俳優ならなんとなくわかっているふうに読むことはできないでもないのだけれども、しかし、疑問をもってしまったら最後、われわれは数ページ以内に収まる「文脈」ではなく、広大な「文化」に踏み出すことになる。
ヤーシャ「可愛いキュウリさん!」(第一幕)
例えば、ヤーシャのセリフで、ドゥニャーシャに対して「可愛いキュウリさん!」というのがあるが、これが文化的にどういうことを意味するのか、宇野重吉の『チェーホフの『桜の園』について』には説明があるにはあるが、作り手がそれを理解したうえで、果たしてそのまま何も加工をしないで、観客のどれくらいにきちんと伝わるだろうか。理解することと、解釈することと、表現することは、それぞれ同じではない。シャルロッタもキュウリをかじる場面がある。現代のベルリンでも、野菜や果物を街でかじっているのを見かけたが、食べ物に対する振る舞いがそもそも違うのかもしれない。
ガーエフ「ポケットを空けて待っているがいい」(第一幕)
それで、「私にわからないことは、おそらく観客にもわからない」と仮定する。しかし、例えばこの前の稽古ではガーエフが金を無心するピーシチクに対して「ポケットを空けて待っているがいい」(神西清訳)というセリフについて私が「セリフのみでは、何を意味するのか、わかりにくいかもしれません」と言うと、「わかると思う人」と「わからないと思う人」とで見解が割れた。このセリフは、内田健介氏の翻訳では「待ちぼうけするがね」となっており、この神西訳のほうが原文に近いらしく、「当てにしても無駄だ」という意味の定型表現らしい。さあ、二口さんにどう演じてもらおうか。
ドゥニャーシャ「まもなく二時。もう明るいですわ」(第一幕)
それだけではない。「まもなく(夜の)二時」が「もう明るい」というのは、日本人の感覚ではまったく理解ができない。「白夜」を知識として持っていたとしても、突然こうセリフで言われて、京都にいて、「ロシアの物語なんだ!」と思える観客がどれくらいいるだろうか。たまたまドイツにいて、日照時間が長い地域の暮しを体験したから「あの感じね」となったものの、そうでなければ「ふーん」と読み飛ばしてしまったかもしれない。あるいは、現実には存在しない、特別な場所だと解釈してしまう(されてしまう)かもしれない。なお、内田健介によると「ドンバス地方」らしい。照明で何か表現できることがあるかもしれない。
第一幕の、それほど目立たないこうしたセリフだけでも、いちいち立ちどまらざるをえない。単純に「意味を理解し、俳優と共有していく」という作業だけでもなかなか骨の折れる作業である。今回は立ち稽古の前に、読み合わせの時間を少し長めにとることができた。俳優個々が最初に持ったイメージも確かめていくことができたために、演出家のイメージを無理に押し付けるということも避けることができているような気がする。
俳優のための芝居・演出家のための芝居
少々乱暴だが、芝居を俳優のための芝居と、演出家のための芝居とに分けるとする。その場合、『桜の園』は明らかに後者に属するだろう
諏訪正「帝劇「桜の園」――危険な単純化」『テアトロ』第502号、1984年、21頁。
(中略)
どの作品でもそうだが、とりわけ読みの深さの問われるのが『桜の園』である。すでに私たちは、たとえば宇野重吉氏の、アナートリー・エーフロス氏の、アンドレイ・シェルバン氏の、読解を知っている。それは方向こそ違え、テキストの深部をえぐっていた。チェーホフは掘り起こされ、一見穏やかにみえる表面からは想像もつかぬ、深層のドラマが発掘されている。
いま『桜の園』を上演する以上、読解の深さがまず問われねばならないだろう。それは俳優の感性を超えてすぐれて知的な操作であり、その知的作業を担当するのが演出家である。『桜の園』が演出家の芝居だといったのはこのためだ。
「演出家の芝居」というよりは、本質的には、「演出家が必要な戯曲」である。体調もあったのかもしれないが、『桜の園』は、とくにト書きにおける余白が多すぎる。だれかが整理する役を担わなければ、混乱するだけなのである。例えば、私が嫌いなト書きがこれである。以下、どのバージョンでも駄目だった。
「いまだに子供部屋と呼ばれている部屋。ドアの一つはアーニャの部屋へ通じる」(神西清訳)
「いまでも子供部屋と呼ばれてゐる室。一つの扉がアーニャの居間へ通じてゐる」(米山正夫訳)
「今でも子供部屋と呼ばれている部屋。ドアの一つはアーニャの部屋へ通じている」(内田健介訳)
「今でも子供部屋と呼ばれている部屋。ドアの一つはアーニャの部屋へと通じている」(佐々木彰訳)
「昔のままに子供部屋と呼ばれている室内。ドアの一つはアーニャの部屋に通じている」(小野理子訳)
「ひとつの部屋、そこは今日まで子供部屋と呼ばれている。ドアの一つがアーニャの部屋へ続く」
(Ein Zimmer, das bis heute das Kinderzimmer genannt wird. Eine der Türen führt in Anjas Zimmer.)
(Peter Urbanによるドイツ語訳、日本語拙訳)
一文目は有名なものだが、私がムっとしてしまうのは二文目である。結局、ドアは、何個あるのか。あるいは何個必要なのか。この扉はカミテにあるのか、シモテにあるのか。例えば、三島由紀夫の戯曲ならこんなト書きがある。
三幕ともブラジル國サン・パウロ市より空路一時間なるリンス郊外の珈琲農園主刈谷義郎の邸宅。二階なる洋風の居間兼食堂。
三島由紀夫『白蟻の巣』1955年初演(『三島由紀夫全集』、第21巻、215頁)
上手に三階と一階へ通ずる階段室。
正面には出口より下手に三つ、上手に一つの窓(その前にディヴァンが置かれてゐる)。
(略)
下手奥には厨房へ通ずるドア。
下手手前に運轉手夫婦の居室に通ずるドアがあり。舞臺の下手約三分の一にわたつて、この夫婦の居室の一部が見える。
『白蟻の巣』の冒頭のト書き、邸宅の説明であるが、これだけで半分である。一方『桜の園』には、文字通りの「間」とか「舞台空虚(舞台からになる)」とか言ったト書きも散りばめられているから始末が悪い。しかも、このト書きにおける「間」は、かなり重要なものであるという意見がある。例えば、ロシア文学者たちの座談会である。
矢沢 ところで僕はみていないんですが、シェルバンの『かもめ』は御覧になりました?
沢崎洋子、中村建之介、灰谷慶三、矢沢英一、安井郁子、山田吉二郎、渡辺哲也、小平 武「座談会 Part Ⅱ 札幌編 テキストとしての〈チェーホフ〉:戯曲を中心に」『えうゐ : ロシアの文学・思想』(北海道大学)第9号、1981年、76頁~78頁。
沢崎 ええ。
矢沢 ああ、それじゃぜひ後で聞かせて下さい。僕はシェルバンの『桜の園』はテレビで見たんですが、見ながら、これはチェーホフではない・・・・・・と感じたのは何故かなということを考えると、確かに紙に書かれた一つの論としてはすごいし、おもしろいんだけど、こと演劇、つまり肉体化しなくちゃいけないというところでどのくらい有効になるか。ちょっと飛躍しますけれど、例えばチェーホフの「間」がありますね。とくに『かもめ』以降間(パーウザ)が非常に多くなっています。ところがシェルバンのあれはほとんど間がないと思うんですね。間を全部取っちゃった。で間を取ったらどういうことになるか。つまり、一人一人の人物が何を考え、何を思っているか、をスポイルしちゃってるんですね。間なんていうものは全部取っちゃって、いわば一種の機械仕掛けの人間みたいにしちゃった。
(中略)
矢沢 それは短いんですか、スピーディなんですか。
沢崎 スピーディですよ。そりゃあ、とても行動的ですね、舞台そのものは。そこが新しいところなのかもしれないんですけれども、どうも・・・・・・どうかしらと思う。
渡辺 まあ、シェルバンのやつはポンポンポンポンいったわけですよ。普通喜劇っていうものは、のんびりしてないわけですね。間がないわけです。ポンポンポンやってる、漫才とか、まあ普通僕らがいう喜劇ってのはね。チェーホフはそこに非常にたくさん間を置いている。ということはね、僕らが考えている喜劇と全然違うわけですよ。しかし、シェルバンだって商人だからね、商人って言えばおかしいけど、やっぱり商業劇団はプラスにしなきゃならないでしょう。面白くしようと思ったら、ポンポンポンポンと台詞を速めていく。これはまあ事実そうなんですよ。おもしろさってのは。のんびりやっちゃ、とてもじゃないけどね、こりゃ喜劇はだめなんですよ。そういう点では僕は何もシェルバンなんかやらなくってもね・・・・・・
小平 うんただね、ちょっとそこで言わせてもらうと、日本人てのはチェーホフ非常に好きだと思うんですね。いろんな意味があると思いますけれど。つまり、チェーホフの冷たさとこうあったかさみたいなのが見えるってのは、ロシアと日本の共同社会に通じてる部分みたいのがあって、それでものすごく好きだと思うんですよ。そういう我々がシェルバンを見たらやっぱり腹が立つってことはわかるんですね。
捕捉しておくと、このシェルバンの『桜の園』演出、『かもめ』演出はそれぞれ1978年、1980年、劇団四季の浅利慶太がルーマニアの演出家、アンドレイ・シェルバンを招聘したものである。当時の『桜の園』公演パンフレットのインタビューにも確かに「テンポをよくするために、間を削ったんです」と書いてあった。浅利慶太は、そのパンフレットのなかで、旧世代の演劇人を「クソリアリズム」と罵っていて時代を感じられる。ロシア文学者たちへの対抗馬として、扇田昭彦によるシェルバン演出の『かもめ』への評を以下に引用する。
二年前の『桜の園』の演出(一九七八年、日生劇場)以来、こうした過剰な演出方法をチェーホフ劇に適用することは、チェーホフを神格化する傾向が今なお根強い精神風土からの強い反発を呼びおこしてきたが、私はむしろこの過剰さをおもしろいと思う。なぜなら、今ますます私たちにとって切実さと新鮮さを増しているチェーホフのゆたかな世界を前にして私たちがなすべきことは、狭く限定された「正解」を求めることではなく、その多層的なゆたかな世界を可能な限り広く深く掘りおこしてみることだと思うからだ。
扇田昭彦『現代演劇の航海』リプロポート、1988年、249-250頁
私は、どちらかといえば、ロシア文学研究者らの肩を持つ側である。70年代以降の大量生産・大量消費演劇の犯行グループの一員である扇田明彦は、「自由」と「無秩序」の境目を、〈芸術性〉というラベルで曖昧にした。この罪は重い。扇田昭彦は言うに事欠くと、「多層的」という用語を躍らせることが多い印象があるのだが、それは単に「いい加減さを許容せよ」という若輩者の「わがまま」にしか、今の私には見えない。
ロパーヒン「皆さん、よろしいですか、発車までに四十七分しかありませんよ! すると、二十分したら停車場へお出かけになるわけです。少々お急ぎ願いますよ」(第四幕)
チェーホフは、しきりに時計を気にする新興商人、ロパーヒンを演じる俳優に、スタニスラフスキーを推していた。結局、スタニスラフスキーはガーエフを演じることになったらしい(内田健介「『桜の園』上演を巡って」論創者、2025年(同訳『桜の園』所収))。このセリフはロパーヒンのパブリックな姿を如実に表すもので、できれば、第一幕くらいに欲しい言葉なのだが、チェーホフはそれほど器用でも狡猾でもない。ただ、チェーホフが、ロパーヒンと演出家スタニスラフスキーを重ねたことには、何か特別な意味が感じられる。
ロパーヒンを書いているとき、この役はあなたの役だと考えていました。理由はどうあれ気が進まないならガーエフを選んでください。確かにロパーヒンは商人ですが、あらゆる点できちんとした人で、完璧に礼儀正しく、知的で、いやしくなく、策略なしに振る舞わなければならない。私にはこの役が戯曲の中心で、あなたなら輝かしい存在になると思えたのです。ガーエフを選ぶのなら、ロパーヒンはヴィシネフスキーに渡してください。芸術的なロパーヒンにはなりませんが、いやしいロパーヒンにはならないでしょう。ルージスキーではこの役は冷たい異国人に、レオニードフでは成金になってしまう。この役の俳優を選ぶ際は、生真面目で信心深い娘のワーリャが愛したことを見逃してはいけません。成金だったら好きにならなかったでしょう。(10月30日)
内田健介「『桜の園』上演を巡って」(同訳『桜の園』所収)論争社、2025年、154頁~155頁。
言葉のうえでは、「輝かしい存在」と言っているが、この手紙の表現を私は素直に読み取ることができない。「お前のような奴にはロパーヒンがお似合いだ」と書いても結果的に希望が通らないのは大人ならわかる。そういえば、チェーホフはモスクワ芸術座によって『かもめ』が再演されることを、嫌がっていたらしい。しかし、結果的には誰もが知る通り、『かもめ』は再演され、大成功をおさめ、演劇史を変えた。複雑な心境のチェーホフを、私は想像する。チェーホフにとって、演出家は、「間」という美しい刹那を形而下のモノで埋めたがり、いいところを持っていく俗物、ロパーヒン(スタニスラフスキー)のように見えていたのかもしれない、と。
確かに、劇作家と演出家(そして俳優も)は、お互いに永遠にわかりあえないものである。「間」の問題についていえば、現実として、舞台上に「間」というものは存在しない。上演中には、美術だとか、小道具だとか、黙って動かない俳優だとか、「何かが、必ず、ある」。演出家はいつだって形而下の世界しか見ていない。演出家の認識の道具は、つねに空間(Raum)と時間(Zeit)のうちにおける「感性」、よくてカテゴリー化するための「悟性」のみで事足りる。「理性」の段階は、じつは演出家には不要である。「超越論的な」「理念的なもの」あるいは「文学的なもの」は演出家には必要がない。もはや邪魔だとすらいえる。
しかし、一人座ってずっと戯曲を書いていると、「超越論的なもの」「理念的なもの」あるいは「文学的なもの」がほんとうに物語のなかに、あるいは舞台の上にあるような気がしてしまう。この感覚の差はきっと永遠に埋まることはないのだろう。ただ、しかし、「間」と書いてみて、何もない瞬間が生みだせるように思ったとしても、上演のときには、実際そこに「何かがある」場合がほとんどである。
カントは、「我々の一切の認識は、感性に始まって悟性に進み、ついに理性に終るが、直観の供給材を処理して、思惟の最高の統一に従わせるものとしては、理性よりも高いもの〔認識能力〕は我々のうちには見出せない」(篠田英雄訳『純粋理性批判(中)』岩波文庫、1961年、17頁)と言っているので、まるでこれでは、劇作家が理性を担う、最も崇高な立場にあるかのように感じられてしまうけれども、結局劇作家も演出家も俳優も、みな等しく単独では何もできない役立たずなので、それぞれに嫉妬や憤怒があっても、受け入れて共存するしかない。ただ、こうした不安定な状況に耐えられない者は少なくなく、扇田が指摘するように「チェーホフを神格化」したり、あるいは「演出家を神格化」しようとしたりすることになる。「神格化」というと大げさだが、チェーホフは、演出家は、俳優は、大人は、労働は、「こうあるべきもの」と思い込むくらいのことは、日常茶飯事だろう。
「間」をとる
とりあえず、チェーホフについて、彼も完璧ではないし、あまりすごい人だと思わない、思わせないようにしなければならない。その意味では、宇野重吉の『チェーホフの『桜の園』について』(麦秋社、1976年)におけるスタンスは気に入っていて、参考になった。
どうせスタニスラフスキーに手紙を書くのなら、そのへんのこと※をちょっとでも教えてやればいいものを、と私などはつい思ってしまうのだが、彼はそれをしなかった。自分の戯曲についてのそのような解き明かしは絶対にしなかった。そのくせ、あとで自分の戯曲をみんなが「誤解」していると言ってこの人は嘆くのである。
宇野重吉『チェーホフの『桜の園』について』麥秋社、1976年、54頁。
※第一幕、第二幕における「汽車の音」問題について。
また演出家というのものは、芥正彦が言うとおり、「一つの余計な悪意、卑猥な邪魔者、社会的には権力と大衆を代弁する二重スパイ、芸術の秘密への嫉妬深いストーカーであり、病的な覗き魔」なので、そもそも誰からもリスペクトされるべき存在ではない。これは私の個人的な思想である。また、扇田の言うような「狭く限定された「正解」を求めることではなく、その多層的なゆたかな世界を可能な限り広く深く掘りおこしてみることだと思う」などというレトリックにも陥らないようにしたい。これは、先述の浅利慶太に倣った思考である。
どちらかといえば、パフォーマティヴな演出を好む私が、コンスタンティヴな作品づくりを志向してきた人間座に呼ばれたことを吟味する必要がある。『桜の園』〈で〉表現するタイプの演出と 『桜の園』〈を〉表現するタイプの演出があるとして、つまり、今回のお題は、良い意味でのふたつの「間(あいだ)を取ることは可能なのか」である。今のところ、何か所かちょこんとパフォーマティヴにした瞬間がある。観る前でも、観た後でもいいけれども、戯曲も併せて読んでもらえると、より深く楽しめると思う。どれほど細部にまで注目できるか、その度合いを高めていくことが、芸術に触れる喜びをもたらす。翻訳は、いまだに神西清訳が名訳として知られ、文庫にもなっていて、手に入れやすい。
PAUSE!PAUSE!
最近知ったことだが、ロシア語で「間」のことを、「パーウザ」というらしい。ドイツ語では、「パウゼ」(Pause)でほぼ同じである。途中休憩のことも、ドイツでは Pause と言う。私は英語でも同じ意味だと思い込んでいたので、以前カナダ人に英語で、途中休憩のことを、Pause と言っても通じなかった。その場にたまたまドイツ語がわかる人がいて、intermission のことだねと助けてくれた。
ドイツ語なら Pauseは、「休符」でもある(英語は rest らしい)。テンポをつくっていくためには、たしかに休符は重要である。シェルバンによる「間を削った演出」がほんとうにただ削っただけなのならば、それはあまりに短絡的だと言わざるをえない。また、前段の座談会における沢崎洋子の発言では、まるで喜劇には「間」がないと言っているように読めるけれども、コメディだろうが、コントだろうが、漫才だろうが、「間」はリズムをつくるうえで重要である。そして『桜の園』には音への要求のト書きがじつに多い。リズムには、理由をつけることが難しい。わかる人には直感的にわかってしまう。ハッキリ言ってしまえば、正解が一つしかない。蜷川幸雄が、2003年のシアターコクーンでの上演パンフレットに「チェーホフの世界は四重奏のようだ」と書いているが、まさにその通りで、いや、この人数ではもはや四重奏に留まらない、オーケストラである。ピーシチクのように何も話していないのに舞台上に居続ける様も、オーケストラの、例えばパーカッション隊に近いところがある。
しかし、これはあくまで比喩である。演劇はオーケストラとは違う。何も役割がないのに、舞台上にいることは「許されない」。それなのに、音楽のようにチェーホフは「書いてしまっている」。もしかすると、オーケストラになりきれない演劇、演劇になりきれないオーケストラともいうべき「半端さ」が、これまで多くの演出家を悩ませてきたとも考えられる。あるいは、この半端さが文学性や神聖性を生み出す原資であり、多くの者に「マイ・チェーホフ」を抱かせる理由なのかもしれない。
稽古では、毎日新しい発見がある。これはいい事のように聞こえるかもしれないが、毎日新しい課題が演出家と俳優の前に出されるということでもあるので、正直に言ってしまえば、「めんどくさい」。だが、本番の日はどんどん近づいてくる。昨日出た課題を終えているわけでもない。そんな稽古が、しかし『桜の園』そのもののように感じられる瞬間すらある。そんな日々で、息つく間がないからこそ、かえって「間」があることの重要性も実感として認識できるようになってきた。
長い前置きになったが、2025年12月6日から7日、京都の府立文芸会館で、私が演出を務める『桜の園』が上演される。ほとんどが今回はじめて創作をともにする俳優・スタッフで、たいへん刺激的な日々を過ごしている。作っては捨てを繰り返す戯曲消費型の日本演劇界にあって、古典戯曲の上演を目にする機会は多くない。『桜の園』のような世界的に名の知れた戯曲の上演は、国際交流のためのプラットフォームとしての役割も持つ。私自身、ロシア系の人々とはかなり話題のネタになった。一言だけ出てくるシャルロッタのドイツ語はもちろん、ちょこちょこ出てくるフランス語も多少覚えがあってよかった。ぜひご来場いただければと思う。