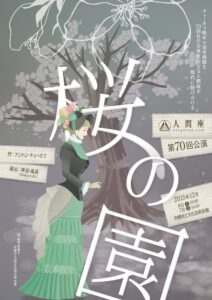【日本 演劇】TIMES(作:林慎一郎、演出:西田悠哉『タイムズ』)――2025年8月25日 京都芸術センター
作:林慎一郎
演出:西田悠哉(劇団不労社)
詳細:https://www.kac.or.jp/events/20250609-2/
観劇日:2025年8月25日 会場:京都芸術センター(フリースペース)
帰国して一発目の観劇が、本作となった。当然、いろいろなことを考えた。
ここで演出のこと以外で、先に触れておきたいのは、「劇場(京都芸術センター)の創造性」と、「劇団」のことである。
「劇場(京都芸術センター)の創造性」
結局私には、最後まで、どうして「今、わざわざ、京都芸術センターが、西田君にこの戯曲をやらせるのか」ということを、理解することができなかった。25周年を迎え、「この記念すべき年を彩る主催公演」として、西田君が演出に抜擢されることにはあらゆる状況からして納得が行くし、戯曲についても、2015年4月の佐藤信演出での上演に、パンフレットなどで触れられていて、演出家の経験が契機となっているということにも合点は行くのだけれども、そこに「京都芸術センター」が介入してくることには、説明が不足しているように感じられた。 これは作品の問題というよりも、場所としての京都芸術センターの問題である。個人的に最近縁遠くなってしまったのものあって、いまどのような方針のもとで運営されているのか、私は追うことができていない。本作だけを切り取ってしまえば、ただ作品が発表されるだけの中身のない箱になっているような印象を持った。 内情に通じているわけではまったくないことを予め断っておくけれども、指摘しておきたいのはこのような公的資金が投じられるいわゆる公共(≠パブリック)の場所を、アーティストの密かな遊び場として隠ぺいしておいて、地域、社会とのかかわりを考慮することをせず、ただ、アドホックに作品を上演させ続けているだけだとするならば、その場所に、持続可能性があるようには思えない。
例えば、「この機会に、どの戯曲を上演するか」というようなクリエイティブな部分をすべて芸術家に押し付けてくることがある。それは一見すると、芸術家を尊重しているように見えるけれども、今の私には「責任逃れ」として映る。京都芸術センターと、西田君とのあいだにどのような協議があったのかは推測の域を出ないが、何のベースもないところから「何かやりたい戯曲ありますか」と突然聞かれて、「じゃ、これで」と彼が答えてこの企画が立ち上がっていったのだとするならば、今後の先行きが不安である。
もちろん、何でもかんでも社会的であれ、というのは、私の偏った考えなのかもしれない。それに、本作が「社会的でない」というのも、私のうがった読みと言われればそれまでである。ただ、この作品はおそらくロームシアター京都でも、THEATRE E9 でも、どこで見ても印象が変わることはないだろう。今回は、俳優の強度が際立ったことで、場所の弱さもまた色濃く見えてしまった。 また、英語字幕が見えやすい座席(中央最後列ややカミテより)だったのだが、字幕にかんしては圧倒的なノウハウ不足が感じられる。必要そうな観客は、私が見たところいなさそうだったのだけれども、ここは劇場として、海外に作品を売り出したいというのならば、きちんと検討してほしいところである。様々な事情があることは容易に想像できるけれども、今回の美術ならば、どの席でも見やすいカミシモ両方の横に配置する余裕はあったように思う。
「劇団のこと」
多くの人が指摘している通り、荷車ケンシロウ、むらたちあきと、劇団不労社の二人が好演だった。他の俳優は、私が観劇したのが千秋楽ということもあってなのか、やや疲れが見え隠れするところがあったのだけれども、両名がそれを引っぱって行くという形は、いわゆる同じ劇団の劇団員として西田君と共有しているであろう相互の信頼関係と実力を証明するものとして受け取ることができた。
「劇団」という形態を諦めた者としては、これがいかに奇跡的な状況であるかということが骨身に染みる。劇団を運営していくのに必要なものは
・それぞれの技術への、相互の芸術的な信頼
・双方納得の適切な金銭的な契約関係
・表現、発表の定期的な機会
といったところだろうか。このいずれか一つでも綻びが出てくると、別のものにも影響し、バラバラと崩れていく。だから、結局、主宰(ほぼ作・演出家)のカリスマ性という「簡単な」統合力に依存してしまうことになる。多くの若手たちが、カリスマ性への依存から脱却した劇団の運営形態を目指しているが、これは「劇団」に限った問題ではなく、「小集団」が常に帯びる性格であり、脱却は不可能である。ときおり「劇団」という名前を別の名前(なんとか集団とか、なんとかグループとか)に変えることで、カリスマ性への依存から逃れようという試みも見受けられるけれども、私にはそれが意味のある試みであるようには感じられない。そして、名前だけ変えたらイメージも変わるかもしれないという希望的観測の浅はかさに気づいた者たちが、個人で活動するか、改めて「劇団」を背負うかのいずれかの覚悟を決めているわけである。
西田演出
西田演出は二作目であった。前回同様、美術の演出に気になるところが多かった。前回のロームシアター京都での「MUMBLE ーモグモグ・モゴモゴー」は私がカミテの端っこに座ってしまったのを差し引いても、横長すぎる印象で「座席によって見え方が変わる良さ」よりも「一部のシーンが見えにくい」ということのほうが強く感じられた。美術は今回も、前回と同じスタッフ(竹腰かなこ)なので、演出家の癖なのか、美術家の癖なのかは今のところわからないけれども、横に広いという点は同様であった。
床にグリッドが出てくるのだが、その演出も見えづらくなってしまっていたので、八百屋にしたり、アップしたりするという工夫が必要だったのかもしれない。八百屋にすると、俳優への負担は増えるけれども、今回の出演俳優たちなら対応できただろう。
衣装で、下半身を黒で統一して、上半身のみ衣装替えしていく演出はたいへん合理的だった。それと同時に、これは日本的な発想なのかもしれないとも思った。腰より下の部分は、男性でも女性でも、日本では古来より隠されてきたからである。スーツを上に羽織るだけで、即座にサラリーマンということを了解し、下半身が状況に対してやや不自然なことが気にならないのは、目まぐるしく場面が転換する作品だからなのだと思うし、この表現を選んだことは高く評価したいところである。
―――――――――
本当は観劇してすぐ書きたかったのだが、帰国直後で身辺があわただしく、1か月以上経過してしまった。しかしやはり、書いておかないと、観たことにできない、またどこかに発表するということにしておかないと書かない性分なので、遅ればせながらダラダラと印象を書いた。これがどこかの誰かの何かの役に立つことを願いたい。
あともう一つだけ小言を言っておきたいのだが、ロームシアター京都も京都芸術センターも、ウェブサイトからのスタッフなどの詳細情報が探しにくすぎる。字も小さいし、改善を強く要求したい。