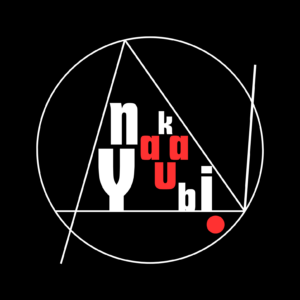【ドイツ 演劇】Carmen(『カルメン』原作:ジョルジュ・ビゼー、演出:クリスチャン・ヴァイゼ Christian Weise)――2025年2月25日 マクシム・ゴーリキー劇場 Maxim Gorki Theater
原作:ジョルジュ・ビゼー
演出:Christian Weise (クリスチャン・ヴァイゼ)
テキスト:リア・ナイト、リンディ・ラーソン
ドラマトゥルク (Dramaturgie) :Endre Malcolm Holéczy, Maria Viktoria Linke
観劇日:2025年2月25日
初演日:2025年1月24日
朝、少しの頭痛にうなされていた。去年はじめてきたときは来た時点から1か月はキツかったが、今回は朝から夜の観劇までゆっくり休むことで回復した。たんに環境の変化ということだけでなく、成長しきってから外国語圏にくると、情報量の多さにあてられたりする。いつもより J-Pop や邦楽が聞きたくなり、U-Bahn に乗りながら、スピッツなんか聞いている。観劇に行かなければならない。とにかく観る。それだけが今確められる、自分の存在理由なのである。
今回、まったく前情報を確認することなく観劇した。『カルメン』は聞いたことがあるくらいで、筋までは良く知らなかった。黒いドラえもんのような恰好をしたスリーピースの演奏。シモテに小さいオーケストラピットがある。指揮者が指揮をするのだが、壮大なクラシック音楽はスピーカーから流れてくる。フリでぜんぶ行くのかと思ったが、そのあとはちゃんとピアノやドラムなど演奏する。今回は中央カミテ端だったので、あまりよく見えなかった。それにしても、アコーディオンは「古き良き時代」のヨーロッパを思わせる楽器である。われわれの文化圏でいうところの、三味線などにあたるだろうか。ヨーロッパの演劇的基礎の一つには、たぶんサーカスのイメージがある。動きや演奏にそれらを強く感じる。ただし、自分が持つサーカスのイメージというのは、結局、フェリーニの映画を通じて得たものなので、正確ではないのかもしれない。
「カルメン」は、フランスの作家メリメによる小説のタイトルで、作家がスペイン旅行したときに思いつた題材である。カルメンは、ピンクの衣装を身にまとっていて、兵士ドン・ホセは黄色の服を着ている。物語は「オペラ」で進行する。しかし、これはたぶん日本なら「ミュージカル」になるのだろう。カルメンはセリフの多くで、英語を使う。自分が観たなかで、ゴーリキーは、作中での英語の使用頻度が最も多い。観劇層が若いとされることと無関係ではないだろう。若者も、最近ではしばしば英語交じりで話すと授業でも聞いた。
昨日の Mother とは打って変わって、今回は、徹底的に動きを戯画化した表現が多数みられた。例えば、カルメンにお付きのものたちが、飲み物を渡す。中身は入っていないのだが、「ゴクリゴクリ」という音が音響効果で拡張される。そしてそれが何回も繰り返される。また最後の場面、ドン・ホセがカルメンを殺害するときには、明らかに白い「形だけを模した」ナイフで、カルメンを刺す。当たり前だがぜんぜん刺さらないし、何度も刺す。カルメンは最後に短く歌う(Auf in den Kampf…)。それを観客もともに歌うように促して暗転という幕切れであった。
ゴーリキー劇場は、音響空間としても、とてもよいように感じる。ちょうどよく響く設計なのだろうか。他の劇場のいくつかの作品では、(自分にとっては)少し広すぎて、音が逃げていくような印象があった。もちろん、劇場に合わせて音響を考えているかどうかという点もあるだろうし、作品ごとに合う合わないもあるので、様々な座席位置で観劇を重ねて検証していきたい。また、舞台はまた映像演出があった。白い美術にいろいろな背景が映し出されて、場面転換を示す。ドン・ホセがカルメンとともに逃走する場面では移動とともに背景が動く。
この作品、次の上演日と次の次の上演日はすでに売り切れていて、私が買ったのも最後の一席(たぶん、ホテルみたいな感じで売れ行きを見ながら調整しているはず)だった。まだ初演されてから1か月しか経っていないなかだと、こうも売れるのか。