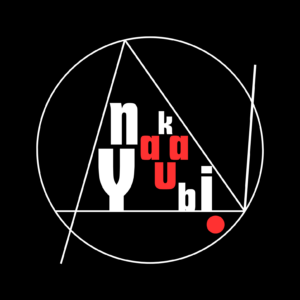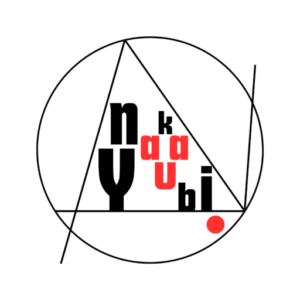【戯曲を読む】No.17 深津篤史『うちやまつり』――なんすか、これ。先輩。(1998年、第42回岸田國士戯曲賞受賞作)
※初演:1997年、12月、伊丹アイホール
あらすじ
背の低い柵でおおわれた小さな空き地。柵を囲むようにして、ベンチ。柵の内側にも椅子が数脚。鈴木が口笛を吹きながら現れる。人々が空き地を行きかう。第一幕 一月三日は午後二時のこと。鈴木と山本の娘(14歳)は、午後十一時にここで会う約束をする。第二幕、一月三日午後十一時、田中(姉)がガラクタのなかからカセットデッキを見つけ出す。カセットテープが入っていたので、聞いてみるとインコの声。何かを録音しているようなのでしばらく聞き続ける。すると何かのきしむ音も聞こえてくる。しかし、確信的なものは何も聞こえてこない。田中(姉)は、第一幕で山田が捨てたゴミを漁る。すると、大量のカセットテープが出てくる・・・・・・
深津篤史(ふかつしげふみ)(1967~2014)
1967年、兵庫県生まれ。同志社大学在学中に第三劇場に入団。1992年、桃園会を旗揚げ。1998年『うちやまつり』で第42回岸田國士戯曲賞を受賞、2005年『動員挿話』演出において第13回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞した。2014年、芦屋市の実家にて死去。享年46歳。
『うちやまつり』白水社、1998年
1998年5月3日、第42回岸田國士戯曲賞の選考会が行われ、『うちやまつり』の受賞が決定した。最終候補作品で私が知っているといえる作品は、永井愛『見よ、飛行機の高く飛べるを』とマキノノゾミ『東京原子核クラブ』だった。選考委員は、井上ひさし、太田省吾、岡部耕大、佐藤信、竹内銃一郎、野田秀樹、別役実である。 太田省吾が「選考会で〈近現代史劇〉と呼ばれた作品群があった」と言っているが、永井愛とマキノノゾミの作品はおそらくこの〈近現代史劇〉に含まれているものと思われる。この二作は技巧に光るものがありながらも、表現としての新しさや芸術性という観点で、『うちやまつり』に及ばなかったと判断されたのだろうと推測する。
『うちやまつり』は、不思議な魅力のある戯曲である。浮いた世界のように見えるのだが、これがわれわれの現実に肉薄したもののように感じられる、といったところだろうか。冒頭から読み始めていると、かなり不安になる。ハッキリ言ってこの戯曲は面白くなるのか、と。戯曲が醸成する雰囲気は最後まで変わらない。日常的な描写、それも家庭のリヴィングや学校、職場といった人々が交錯し、何かがつねに行われる場所でもない、不安定な場所設定がこの戯曲を規定する。背の低い柵でおおわれた小さな空き地。それは団地のなかにある。
「背の低い柵」はそして、登場人物によって簡単に乗り越えられてしまう。そこにはカセットテープがあり、何かを録音(おそらくは盗聴)しているようである。人物たちが聞くが、何か確信めいたものが出てくることはない。また、空き地の下には、インコ、飼っていたサルが埋まっていることが示唆されたり、団地で起きた殺人についてなどが話されるが、これらも確信をついてストーリーを動かすようなことは一切ない。 気になることはたくさんある。しかしそのどれも「確信をつかない」。登場人物の名前は、鈴木、佐藤、佐藤の奥さん、山本さん、山本さんの娘さんなど、徹底して「匿名的」になっていることも、「記憶に残らない」現実を描写するためのギミックなのだろう。 あとがきには、「愛されないし、愛せない。これが僕のスタート地点である」(あとがき、124頁)とある。現実とは、実はそうなのかもしれない。人間は人生のうちで数えきれない他人とかかわるが、そのほとんどから「愛されない」し、そのほとんどを「愛せない」。しかし、物語は多くの場合、この現実を捨象して「愛すること」を抽象化して描く。チェーホフのような技巧だが、日本で、日本語でやるならこういうことになるのか、とも思った。
やや中途半端に思える関西弁(標準語が混じっているような印象もある)が、ことばの希薄さを高める。標準語だけだと、もっと漂白された印象になったのかもしれないのだが、それだと人物間の差延を調合するのが不可能になるかもしれない。そしてこの感覚は、理解できるような気がする。私が在籍していた頃も、第三劇場は京都の学生劇団だが、日常から標準語よりの言葉が多かった。自作や先輩、後輩の作品も思っていたより、関西弁で話す演劇をやることは少なかった記憶がある。同志社大学は京都にあるが、学生たちはいろいろな地域から来るので、この妙な、土地から浮いたような感触の関西弁が生み出されるのかもしれない。