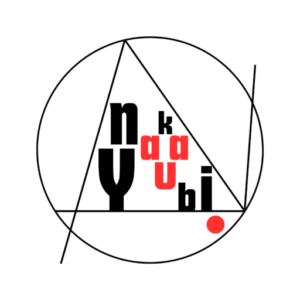「名前のない星」戯曲賞――最終選考前の所感(2025年1月24日)
「名前のない星」戯曲賞 ←詳細はこちらのリンクから
最近、旧字体で書かれたような古い戯曲ばかり読んでいたので、今現在の作家の言葉で書かれたものを読むことは自分にとっては、とても新鮮だった。私事になるが、ベルリンで語学学校の授業を受けながら、昼からは日本語の戯曲を数本読み、そして夜にはドイツ語や英語の演劇を観に行くという日々が続き、体力をもっていかれた。とはいえ、自分がこれまで戯曲賞の審査の講評に感じていた疑念を払拭したいと思っていたので、なるべく読んだものには評をつけることにした。何かを指摘するときにはできるだけページ数付きでどこのことなのか具体化することを心掛けている。自分が逃げられないようにするためである。よくわからないざっくりとした印象を、しかも、多く人が演劇を評するときのような使い古された軽い言葉(「やりたいことはわかるッ」のような)で書かないようにした。
ただし、結局すべては印象に始まり、印象に終わってしまう。「それってあなたの感想ですよね?」は効果覿面で、すべてを無に帰する。しかし主観と客観の狭間で、われわれは闘うしかない。そもそも、それがあらゆる人文知の条件なのである。自然科学も、結局は人文知を通って、偏見や思い込みを解消する必要に迫られる。
最終候補作残っているものについては、すべて声に出して読んだ。1つ、2時間としても、8作で合わせると、読むだけで16時間かかる。一次審査のときには、個人的なルールとして、1作につき、2時間で読み終えること、評を書くことを併せて終わらせると決めて、自分なりの公平性を維持できるように意識した。また、私が読んだすべての作品で、Notion が有料で提供する Notion AIに文字情報を入れたうえで要約させ、それを参照しながら読み進めた。AI要約の精度はそれなりだった。作品の長さの幅が大きいので、公平性を保つやり方としては、これが限界だと思われる。審査することのたいへんさも理解したが、他の戯曲賞の審査員は私よりは才能のある方ばかりだと思うので、その仕事を受けるからには、後続のためを思って、内外にわかる形で、そして「それってあなたの感想ですよね?」に屈することなく、真剣に、手を抜くことなく取り組んでほしい。
なお、「好みの戯曲はなかった!」。そのためフラットな視点を持つのは自分としては苦ではなかった。私の「好み」の作品とは、オリジナリティにあふれた、性格の悪い人間観察眼と過激な政治的主張や極端に歪んだ社会への意識が含まれているものなのだが、そういうものがなくて胸をなでおろし、ホッとした。
本戯曲賞にお送りいただいた作者の皆様へ。
ありがとうございました。私の書いたことや発言したことのなかで、糧になるものがあればそれでよし、なければ即座に忘れればいいと思います。ごちゃごちゃうるさい一読者くらいに思って、各自、都合よく捉えてください。一次・二次・最終の選考に残ろうが残るまいが、賞を取れようが取れまいが、少しでも私の言葉で気になることがあれば、いつでもお声かけください。会ったことがない方ばかりです。どこかでお会いすることがあれば、そのときは、どうかお手柔らかに。
2025年1月24日
神田真直(Nakayubi.)