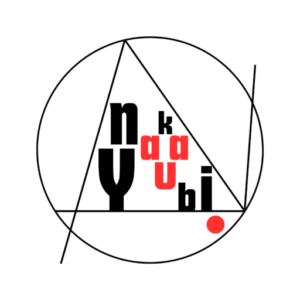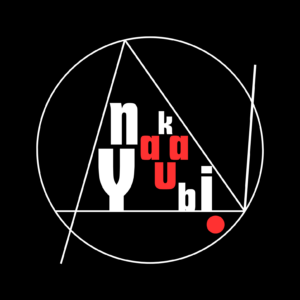【戯曲を読む】No.16 マキノノゾミ『東京原子核クラブ』初演:1997年――内容と思想について
マキノノゾミ『東京原子核クラブ』小学館、1996年(単行本) ←神田が読んだほう
マキノノゾミ『マキノノゾミ(1) 東京原子核クラブ』ハヤカワ演劇文庫、2008年(文庫)
あらすじ(一幕だけ)
第一幕。
昭和七(1932)年、七月。友田晋一郎は、理科化学研究所に勤めているが、自分が「井の中の蛙」だったと痛感し、研究所を辞めて京都に帰ろうとしている。しかし、同僚で、同じ「平和館」に住む武山真先から、主任研究員の西田義男が、友田の仮説を高く評価していたことを聞き、また戻ることにした。
昭和八(1933)年、十月。平和館の住人の一人、谷川清彦は検閲のために芝居の上演が中止になったうえ、経理係にお金を持ち逃げされたらしく、かなりやさぐれていて、同じく住人で、友田の同僚でもある小森敬文に突っかかる。その日は珍しくカレーライスだったのだが、外でキャッチボールをしていた橋場のボールが母屋に飛び込み、カレーがだめになってしまう。
昭和九(1934)年、五月。武山の友人で、海軍中尉の狩野良介が座っている。武山と再会し、身の上話に始まった狩野との話題は、武山の研究内容に移る。それは原子核に関するものだった。小森が現れ、西田に放置されていた友田の論文が、同じ内容で他の研究者に先を越されてしまったということが明らかになる。その後、西田が、友田を訪ね、部屋で土下座して謝罪する。
昭和十(1935)年、九月。橋場が便所にこもって出てこない。先日の試合で、橋場の大活躍のおかげで、早稲田に東大が勝利を収めたが、その脚光のために橋場がニセ学生であったことが判明した。試合は没収試合となり、大きな騒動となったことに橋場は責任を感じているのである。住人一同困り果てていたところに、東大野球部員の林田清太郎が現れ、話をすると橋場がようやく出てきて、林田は橋場にウィニング・ボールを渡して去る、一見落着の感。しかし舞台は、時代の暗い様々なニュースに飲み込まれていく。『二・二六事件』、『盧溝橋事件』『ノモンハン事件』・・・・・・
第二幕
昭和十五(1940)年、十月の終わり。・・・・・・
マキノノゾミ(1959~)
劇作家・演出家。同志社大学文学部卒業。1984年、大学卒業を機に劇団 M.O.P を旗揚げ。初期はつかこうへい作を上演していたが、1989年からオリジナル脚本を執筆しはじめ、以後精力的に作家兼演出家として舞台作品をつくる。小劇場、商業演劇、新劇とジャンルを問わず活躍。
Note1 内容について
かなり省略して書いたが、それでも第二幕まで書いてしまうと問題が発生するおそれがあるのでここまでにしておく。 下宿のサンルームも兼ねた談話室、という人が入れかわり立ちかわりしやすい場所を設定した時点で、かなり作劇的に自由が与えられたことだろう。ただ、書きやすくなっただけでは、最後まで飽きないエンターテイメントを提供するのは難しい。しかし、犬のガロア、キャッチボール、便所、早坂のジャズピアノ、母屋の桐子といったいろいろな仕掛けが、その場その場で小気味よく作動するので、最後まで楽しんで読むことができた。
繰り返し使用される「短い間」というト書きが、空間における会話のテンポを規定する。当然、「短い間」に埋めるべきものは、ただの空白ではない。多数の人間が織りなすやりとりのなかで、空気がほつれたり、むすばれたりするときの感覚は、俳優との共同作業を続けているなかで得たもののような気がする。稽古場に近い場所で書かれたのだろう。
この本には、註がたくさんあって、それが稽古場の裏話のようなものであふれていて、それも十分笑わせてくれる。第一幕の最後にはこうあった。
「ところで、ここまで書き終えた時点で第一幕の四場面すべてが同じストーリーパターンであることに気づいた。登場人物の一人が何らかの理由で落ち込んでいて、その人物が最後に少し癒されて終わるのだ。好きなパターンとはいえ、かなり画一的である。「何てこったい、このままじゃマズいぞ、何とかして違うパターンも作らねば」と内心かなりあせった。そのせいだろうか、ここで筆はピタリと止まり、稽古初日にはここまでしか台本が出来上がっていなかった。完成したのは初日の十日前である。
マキノノゾミ『東京原子核クラブ』小学館、1996年、82頁
こういう話をあけすけに話してくれる作家は少ない。しかしこれを読んで、二幕どうするんだろう、といっそうワクワクしてページをめくることができた。また、どこでのお話か忘れしまったが、結末を考えずに前から書くタイプらしく、その意味で受け手と同じ気分で最後までいられるのは羨ましいなと思った。もちろん、二幕の、みんなが喪服姿なので、彦次郎が亡くなったと思いきや実はガロアだったという場面などは、一部とはいえ、先を知りながら書く手法に決まっているのだろうけれども、同じように結末を決めずに前から作品を書いていくものにとってはマキノノゾミの戯曲は、一つの参考になるのかもしれない。
Note 思想について
この戯曲を読みながら、2024年に鑑賞した映画『オッペンハイマー』を思い出した。この物語の中心人物である友田晋一郎は、ノーベル賞物理学者の朝永振一郎博士であるが、状況が違えば、彼らは「オッペンハイマー」になっていたのかもしれないということである。20世紀の人類史を決定づけた原子力にまつわる事象について、われわれは永遠に無邪気ではいられない。
「政治の面でいうと、今日私たちが生きている現代世界は最初の原子爆発で生まれたのである」
ハンナ・アレント(志水速雄訳)『人間の条件』ちくま学芸文庫、1994年、17頁。
本作は、第42回の岸田國士戯曲賞にノミネートされていたが、岸田賞受賞はならなかった。同年にノミネートされていたのは、大森寿美男『男的女式』、鐘下辰男『寒花』、高泉淳子『こわれた玩具』、永井愛『見よ、飛行機の高く飛べるを』、長谷川裕久『美貌の流星』、深津篤史『うちやまつり』で、受賞は『うちやまつり』だった。
選考会で〈近現代史劇〉と呼ばれた作品群があった。〈うまい〉作品はここに集中しているのだが、演劇の根底的必要が感じられず、そこで扱われている〈歴史〉は、興業的安定の素材のように感じられた。
太田省吾「〈ふつう〉の受容力」白水社、1998年、4頁 ※
今回の候補作には、『歴史』を扱ったものが多かった。『歴史』を扱う作品は、安易なものと、苦労が偲ばれるものに分かれがちだ。安易な作品というのは、『歴史』が『人間』と結託して、予定された『テーマ』へ向かう・・・(略)・・・永井愛氏の〈見よ、飛行機の高く飛べるを〉は、台詞は小気味よいけれど、やはり『ヒューマニズム』に着地している。その点で、マキノノゾミ氏の〈東京原子核クラブ〉は、原爆を作ろうとしているエリートに目をつけたのは、してやったりであった。だがその後に苦労が偲ばれない。 『歴史』や『人間』で終わらない物語が見えてこない。
野田秀樹「井上ひさし氏が、遅筆な訳」、白水社、1998年、7頁 ※
※いずれも第42回岸田國士戯曲賞講評で、『うちやまつり』(白水社、1998年)の付録
野田・太田の言おうとしていることは、なんとなくわかる。もしここに、クリストファー・ノーランの『オッペンハイマー』が入っていたら、同じような評を受けたのかもしれない。もちろん、何の政治的意図もなかったというわけではなく、初演時のパンフレットには、ここで描かれている時代が、モデルとなっている朝永の青春期というだけでなく、日本の青春期であるということに、作者は触れていて、「おい、それって少しマズんじゃないかい?」という思いを込めたとのことなのだが、野田・太田には届かないものがあったのではないかと推察する。また、タイトルから受ける印象は、かなりドぎつい政治劇かもしれないが、それにしては明るく読むことができる内容である。そして、私もある面ではウェルメイド・プレイで、田坂具隆監督『女中ッ子』(映画、1955年)のようなヒューマニズムの物語を愛していながらも、どうしても別のエッセンスを加えたくなってしまう性分である。演出するとしたら、作者が嫌がるような何かをしてしまうだろう。
なお、このときの岸田國士戯曲賞の講評はかなり読み応えがあって、とくに別役実のテキストは、現代劇について鋭い洞察を短く書いたものである。しかし、そのことについて考えるのは、『うちやまつり』を読むときにに譲りたい。