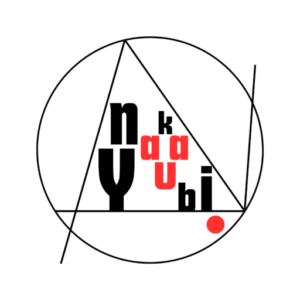劇団辞めてドイツ行く(60)カンティーネと〈公共性〉――2025年8月5日
ざわめくpopulus
ベルリンの劇場に行くなら、作品だけでなく、カンティーネ(食堂)にも注目しなければならない。私はマクシム・ゴーリキー劇場のカンティーネがいちばんのお気に入りだが、シャウビューネ、ベルリナー・アンサンブルも悪くないし、ドイツ座のバタープレッツェルはとてもおいしいので、行くとほぼ必ず注文する。カンティーネは、開演前後だけでなく、一日中やっていて、終演後も日付が変わるまで居座って野村と議論したりしたし、とりあえずカンティーネ集合で!と待ち合わせ場所にも便利だった。
そこでは、観客だけでなくスタッフ、演出家、出演前後の俳優も雑多に入り混じり、友人同士なら状況に構わず議論やおしゃべりに興じる。私はこの様子を見て、「これが先生が言っていた、パブリック(〈公共性〉)というやつか!」と10年前に大学で受けた講義のことを思い出していた。
公共 ≠ public
われわれ演劇人は、不況やコロナ禍など、社会において分が悪くなると、すぐさま公共性という便利そうな概念に飛びつくようになった。「なぜ演劇に税金を投入するべきなのか」と言われたら、「公共性があるから」というお決まりのパターンである。しかし、「〈公共性〉とは何か」という根本的な問いは、しばしばはぐらかされる。おそらく、この議論はどうしても哲学や政治学の領域に入ってしまい、日本の演劇人同士で共通認識を持つのが困難になってしまうからだと思われる。これは芸術家という括りにまで領域を拡大させても同じだろう。
公共性論の講義を思い出す。“public”の概念を学んだ。当時はこれが演劇にかかわってくるなど思いもしなかったが、ベルリンの劇場に通って、ヨーロッパにおいてあのとき学んだ“public”が具現化されているのをこの目で見、感銘を受けた。置き去りにされがちな、公共性論(講義の英題は”Public Sphere” =「公共圏」だった)とベルリンの劇場の風景を重ねてみる。
よく知られているように、明治期、さまざまな西欧の概念語を漢字で表せるように多くの日本語が作られた。教科書で西周がphilosophyを「哲学」と訳したのは有名であろう。public が「公共」と訳された経緯について、私は正確に記述することができないが、このようにして大量に漢字を当てて行くなかで、歪が起き、理解に不足が生まれた概念は少なくない。
「哲学」という訳語も、問い直すことができなくもない。柿本先生はある論文のなかで「問いを愛すること」という言葉を使っていて、これに私はひどく感動した。この言葉のほうが正しくphilosophy を表していると思ったからである。
「公共」という文字には、上下関係が内包されているという。しかし、“public” にはどのヨーロッパの言語を見ても、上下関係の意味合いはない。ラテン語やギリシャ語にまで遡っても、単に、雑多に集まる人々であって、上下関係を表すものではない。だから、公共≠public ということを意識することからはじめなければならない。このような説明から先生の『公共性論』は始まった。
むろん語源が、人々の行動を制約するわけではない。しかし、哲学、芸術、そして公共といった概念語を扱った議論をするときに、その本来の意味を確認しないでいるべきではない。そもそもこうした言語は、ヨーロッパの独自の文化に由来する、ヴァナキュラーなものであって、普遍的なものではないからである。public は、populus (人々/people)を経て、派生した単語である。そこには単に、人々がわちゃわちゃ集まっているというニュアンスしかない。ドイツ語学習者御用達のウェブ辞書 DUDENでは、publik に対して、由来に publicus とあり、さらに、öffentlich という説明も含まれている。öffent-lich のöffen は、動詞 öffnen (開ける)から来たものである。独和辞典では、形容詞 öffentlich は単に「公共の」と記載されていた。それでは「公共」を広辞苑で見てみる。しかし、そこには「社会一般、おおやけ」としか記載がなかった。あまり説明になっているとは思えない。
しかし、「公共性」の項目に移ってみると、「広く社会一般に利害や正義を有する性質」と書かれてある。どこで、「利害」や「正義」という意味合いが加わったのだろうか。「公」という字は、「私」の対義語として紹介される。日本の「公共」というハコのなかには、いったい誰がいるのだろうか。
ベルリンの劇場には、しかし、「人々」の意味に由来する〈publik〉がいたような気がする。また同時に、彼らがいる場所は〈öffentlich〉でもあった。そこには、ざわざわとした市民たちだけしかいなかった。そして、俳優も、演出家も、観客と同じ一市民であるという意識は、カンティーネでこそ感じられるものであった。どんなスター俳優でも、同じ場所で食事したり、お友達と話している。少なくとも、日本よりも、観客と作り手のとあいだに隔てられたものを感じにくい構造であるように感じられた。著名な国民的な俳優でも、「あの、ちょっと写真撮りたいんでどいてもらえます?」と言えるような雰囲気がある。
この雰囲気は、日本からきた私からしてみれば、異様とさえいえる。日本では演者と観客には境界線がある。能など、われわれの伝統芸能においては、舞台上の〈存在〉はわれわれと同じ〈人〉ではない、という認識がある。あるいは、もしかすると、不倫や犯罪行為やハラスメントを少しでも疑った時点で、即座に永久追放する現代のほうが、舞台上の〈存在〉が〈人間性〉を帯びることを嫌悪しているのかもしれない。
もちろん、キャンセル・カルチャーが存在しない場所も時代もない。しかし、近代社会は本来、キャンセルされたあとでも、戻ってくることができる仕組みである。罪を犯したとき、それ相応の罰が与えられるというのは厳密には近代社会ではない。刑務所で行われるのは、社会に戻るための再教育である。社会にいるのは、教育され、社会でともに生きていくために必要なことを理解した者だけであり、だから秩序が維持され、誰もが安心して過ごすことができる。それが近代社会の理論である。当然、理論はつねに現実と乖離してしまうのだけれども、少なくともそのような論理立てであることを踏まえると、罰というのは前近代的で、野蛮な発想と考えることもできる。だから、日本社会が、殊更「懲役」などといって、罰の側面ばかりを意識させていることに、近代社会の理論との齟齬があることは指摘されねばならない。
近代社会では、publik も öffentlich も成立させられる。人々は十全に教育され、秩序維持のための知識があり、場所は開かれていても問題がない。そのような場所の一つが、あるいはその周辺までが発達した社会であることを確認できる場として、劇場が機能しているように、カンティーネでは感じられた。
ゴーリキーで観劇した『舞台罵倒』という作品では、以下のような場面があった。俳優たちが観客に質問をし、該当する者は立たいる。質問がなかなかに尖っていて、例えば「月に1000ユーロ以上稼いでいる人は立って」と言って徐々に金額を上げていく。もちろん、立っている人は減っていく7000ユーロくらいまでいったのだろうか。最後まで立っていたのは投資家の老紳士だった。観客の社会的地位を可視化するという趣向である。そのなかで、一人の女性の俳優が、「女性を愛する人」→「未婚の人」→「いまパートナーがいない人」と聞いていき、残った男性を見て「オッケー、カンティーネで会いましょう!」と言った。日本ではジョークであることを強調しないと、だいぶ無理な演出であることを認めねばならない。
日本でもまだ喫煙所だけはそういう場として機能しているかもしれない。というのも、KEX でフローレンティナ・ホルツィンガーが『tanz』をやっていたとき、終演後、喫煙所で彼女が観客の誰かと談笑しているのを見た。著名な作家でも、観客に混じってそのへんをうろちょろしている。もちろん、話しかけられるかどうかはこっちの勇気次第だが、妙に気遣うことなく、雑多にわちゃわちゃしている感じは、“public” のイメージに合致する。
ハーバーマスとアレントの縫い目
ここでようやく、私はハーバーマスとアレントについて述べる。ふつう、公共性論を扱う場合は、彼らの著作からはじめるものなのだが、それらはあまりにも抽象的で、手触りからかけ離れすぎていて、とっつくきにくい。中世のサロン文化とか、ギリシャの民主政などと言われても、歴史のお勉強にしか感じられない。しかし、ここまで書いてきたような劇場のカンティーネの姿から入ってみれば、もう少し〈公共性〉“public” のイメージを確かめやすくなるのかもしれない。
ハーバーマスやアレントが重要になってくるのはむしろ、ヨーロッパ由来の“public”概念の限界や隠ぺいされている現実を理解するためである。18世紀のサロン文化の公共圏でも、ギリシャの民主政の世界でも「表面的には誰も排除していないが、実際には、多くを排除している」。劇場も同じである。表面的には誰も排除していないが、実際には多くを排除している。むしろ、排除できているからこそ、安心して、議論・発言することができる。もはや家族よりも、劇場のほうが安心して議論できる可能性すらある。そんなものを求めて、劇場に集まるのは、『舞台罵倒』の例でも示された通り、高所得者や富裕層、インテリ層に限定されている。
「どなたでもどうぞ」よりはマシかもしれない
それにしても、このようなスタンスにもそろそろ飽きてきた。岸田國士など、男性作家の戯曲を、いわゆるその「男性性」から切り崩していくのは恐るべきほど簡単であるのと同じように、社会を、その限定性から批判することはありふれたものである。ましてや劇場という収容人数制限がある物理的空間に、参加できない人間が出るのは当然のことである。「どなたでも」の果ては日本で飽きるほど見てきた。それは高校受験のときからで、参考書の1ページ目に「このテキストは高校生だけでなく、大人の方も…」とあるテキストが散見された。きっと出版社が少しでも裾野を拡げたくて「はじめに」でそう書くように要求したのだろうけれども、これでは、いったい誰に向けているのか、わからなくなる。意思決定過程を曖昧にし、責任の所在が不明瞭になりがちな、日本の制度や施設のほうが、「表面的には誰も排除していないが、実際には多くを排除している」ことを巧妙に行っているように思える。
結局は開かれ具合と、閉じ具合が明らかどうかということが、自分にとっては重要である。その点でいえば、階級意識が色濃く残るヨーロッパのほうが露骨で単純に見える。そういえば、おりぴぃが言ってたこと、結構その通りだったな。考えるだけの日々にも飽きてきた。いい加減、何か作品を発表したい。とりあえず、戯曲を書こう。