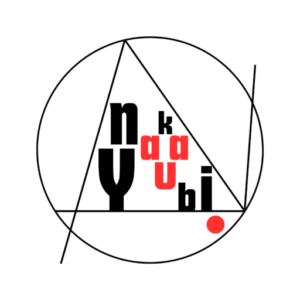【戯曲を読む】No.15 田中千禾夫『教育』1954年
田中千禾夫『教育』(教育・笛他一篇 戯曲)河出新書、1955年
あらすじ
外科医を志望し、病院で勉強している禰莉と、その母絵礼奴のもとに、瑠王が月々の生活費を渡しに現れていた。瑠王は、禰莉の父、絵礼奴の夫である。絵礼奴は瑠王と同じ空間にいることを強く厭い、自分から退出してしまう。瑠王は禰莉に、自分は本当の父親ではなく、本当の父親は、絵礼奴が禰莉を身籠ってすぐ肺炎で亡くなった仏蘭西亜という友人だったことを明かす。そして絵礼奴と瑠王は肉体関係を持つことなく、今日まで過ごしたのだという。これを聞いても、禰莉は、瑠王を父親と信じようとする。瑠王は、酒飲みの自分の老い先は短く、来月からは公証人が代りに金を持ってくる、今夜にも港を立つ、もう二度と会うことはあるまいと言い残して、去る。
瑠王が去ったあと、翡江流が現れる。翡江流は、禰莉が働く病院の医者で、二人は先生と助手という関係である。翡江流は妻がいるにもかかわらず、禰莉に好意を持っている様子であるが、禰莉のほうは、翡江流のことを、男として意識したことがないとわかる。翡江流が自嘲しているところに、絵礼奴が帰ってくる。禰莉が席を外しているあいだ、翡江流は、医者として身を立てようとする禰莉について、「普通の女性としての道」も通るべきであると、絵礼奴に主張するが、禰莉が戻ると話は途切れる。翡江流は足早に退場。
翡江流が去ると、禰莉は、瑠王が「あんな風に」なったのは絵礼奴の所為だと言って詰め寄るが、絵礼奴は別の真実を話す。確かに絵礼奴は仏蘭西亜を愛したが、彼の死因は肺炎ではなく、転落死だった。それが事故か他殺かはもう分からない。そしてその後、瑠王と結婚した、と絵礼奴は説明し、瑠王を一度も裏切ったことはないという。禰莉は「じゃあたしは、誰の娘?」と聞いても、絵礼奴は「黒い天使よ」と返す。
絵礼奴は神秘的な何かに囚われ、いつかの夢を今も見続ける。禰莉は、結局自分は瑠王の娘であることを信じる。絵礼奴の「神の如く醜悪なる」「演技」を、少なからぬ努力を以て無視しながら、禰莉は何やら音読しながら読み耽っている。禰莉が扉を開けてやると、絵礼奴は吸われるように消えてしまう。それでも絵礼奴の、子守歌の歌声が聞こえる。禰莉はボードレールの詩を読むが、やがて低い声で「目的を下さい・・・・・・眠らなければ・・・・・・眠らなければ、一つになれない・・・・・・・そんなのいや・・・・・・いやです・・・・・目的を・・・・・・目的を・・・・・」と呟き、「烈しい苦行に身を投ぜんとするかのように、禰莉の額が何者かに突っかかって行く。幕。
田中千禾夫(1905-1995)
長崎県長崎市生れ。1923年、慶応義塾大学仏文科予科に入学し、在学中に岸田國士らが始めた新劇研究所の研究生となる。1933年、第一次《劇作》の同人に加入し、編集実務を担当。デビュー作は戯曲『おふくろ』(1933)で、川口一郎演出により、築地座で初演。『教育』(1954)などで、1955年、読売文学賞を受賞。そのほかの代表作に『マリアの首――幻に長崎を想う曲――』(1959、岸田演劇賞受賞作)があり、関西歌舞伎での『お國と五平』(1949年)演出など、演出家としても活動。『物言ふ術』(1948年、《劇作》で一年連載)『劇的文体論序説』(1977)などの理論面での著作もある。長きにわたり、岸田國士戯曲賞の選考委員を務めた。カトリック信徒であることでも知られる。
ノート
この戯曲を読んで少し時間が経ったあと、日本演出者協会のイベントで、再び田中千禾夫を読むことになった。しかし、『教育』と『幸運の葉書ー別の名「女豚S」ー 』とでは、まるで印象が違って、松田正隆『月の岬』を読んだあとに『文化センターの危機』を観たときのように、私は面食らった。ただし、『冒した者』をかつて俳優として読んだ経験から、当時の新劇に類する劇作家たちが何に葛藤を抱いていたのかはなんとなく想像がついた。
『ゴドーを待ちながら』が翻訳、出版されるのは、1956年で、1960年に日本で初演されるのだが、同時代人たちは、イプセン、チェーホフら自然主義の演劇の形式に疑問を抱きつつあったように思う。しかし、「新劇」は、旧態依然とした歌舞伎などの日本の伝統芸能やり方を否定するところから出発してしまった以上、容易にそれを参照することはできない。輸入されてきた、戯曲やスタニスラフスキー・システムという、非常に厳しい縛りのゲームを余儀なくされていたのだろうと『冒した者』の壊れ具合を見ると想像している。そしてこの『冒した者』の壊れ具合によく似た様相を呈していたのが、『幸運の葉書ー別の名「女豚S」ー 』だった。
『教育』は、それとは対照的に、構成がしっかりとらえやすく、名前が禰莉とか、絵礼奴とか当て字で書かれてある以外は非常に読みやすい。三島由紀夫は、『サド侯爵夫人』(河出書房新社刊、1965年)によせた跋のなかで、「日本の新劇俳優の翻訳劇の演技術を、逆用してみたいという気があったのだ」。「もっともこれは別に私の発明ではなく、すでに田中千禾夫氏が『教育』で試みて成功している」と書いている。これが私が本作を手にとったキッカケである。そして別のところで三島は、作者を「正堂な岸田國士氏の後繼者」(1)と位置付けた。挑戦的な姿勢は結構なのだが、そういう部分はアングラ世代たちに任せてもよかったのではないか、と『教育』と『幸運の葉書』を読む限りでは思ってしまった。
また別のところになるが、田中千禾夫には、個人的にはあまりいいイメージがない。谷崎潤一郎『お國と五平』の上演史を調べていたところ、谷崎本人にディスられている若手演出家がいて(2)、それが田中千禾夫であったからである。もちろん、本人が若かった頃というのもあるかもしれないが、個人的には『教育』の仕事だけがいい仕事という印象に留まっているので、他の高く評価されている戯曲にも触れていきたいと思う。
(1) 三島由紀夫「田中千禾夫氏の戯曲「教育・笛」」(『三島由紀夫全集 第26巻』、新潮社、1975年、557頁)
(2)谷崎潤一郎「お國と五平所感」(『谷崎潤一郎全集 第三十巻』中央公論社、1959年)