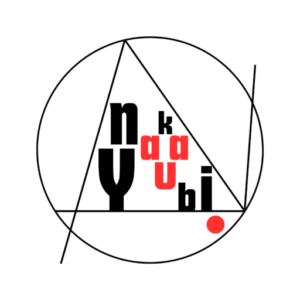【戯曲を読む】No.11 鈴江俊郎『あおく見えるのは空と』 初演:1995年
あらすじ
病室の夫婦。夫は骨折で入院。妻はいつもと少し変わった日常に新鮮味を覚えている。妻は、双眼鏡でいつもと違う視点から町を眺め、たまにレンズをいじって七色に映る空や夫を見る。病室は煙草の臭いがする。谷本さんという隣の患者が隠れて吸いに来ている、自分はやめたと夫は嘘をつく。さらに夫は看護婦を口説いていた。そればかりでなく看護婦以外にも浮気相手がいるという。あるとき、夫は看護婦から谷本が肺癌の患者であり、手術中であることを聞く。それを知らなかった夫は後悔する。妻が現われ、谷本の死を知らせ、夫婦は悲しみに暮れる。退院の日。荷物をまとめ、先に出ていく妻を見送り、「退院したら別れるんだろ、そう考えてるんだろ」とつぶやく夫だったが、煙草を急いでもみ消し、病室を後にする。と、思いきや慌てて煙草をもみ消したコップを取りに戻る。そして再び病室から出ていく。おしまい。
鈴江俊郎(1963-)
大阪出身、京都大学経済学部卒業。京都を拠点に活動し、松田正隆、土田英生ととも雑誌『LEAF』を発行。1995年、『ともだちが来た』で第2回OMS戯曲賞を受賞、1996年、『髪をかきあげる』で岸田國士戯曲賞を受賞。
ノート
病室というかりそめの空間で過ごす時間は、日常を少し違った視点から眺めることを可能にする。そうして夫婦は、お互いの関係に、すれ違いながらもあれこれと思いを馳せる。「ドキドキしている」というセリフからわかるように、妻はそのずれた日常にかえって新鮮さを覚えている。セリフの文体は、軽妙で柔らかいながらも、隠された本性が少しだけ見え隠れするように書かれている。入院という短い非日常が、日常の様相をあぶりだす。それさえも、現代人にとっては生活一般のありように思える。日常は劇にしにくい。これは、自然主義の持病である。そしてこの自然主義を克服するためには、そこから脱出する一つの仕掛けが必要で、本作の場合は病室という非日常空間で起こる出来事を主題とすることで、登場人物が新たな歩みを進めようとする。しかし、結局それはどっちつかずの日常への回帰にすぎないという結末である。妻が手放さない双眼鏡は、本作全体を占める作者の目指したもの=「日常の焦点を変える」ことのメタファーである。ト書きは文学的ではあるが、柳美里のような空間への意識をもとにした叙事的なものとはちがって、登場人物の意識をもとにした抒情的なものが多く感じられる。