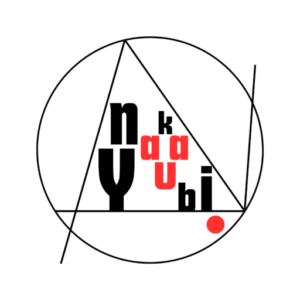【戯曲を読む】No.9 鴻上尚史『朝日のような夕日をつれて 21世紀版』(2014年) 初演は、1981年だが・・・
鴻上尚史『朝日のような夕日をつれて 21世紀版』論争社、2014年
おもちゃ会社「立花トーイ」。社長はじめ、社内では新しい製品の開発について話し合われる。
「ゴドーを待ちながら」を模した世界では、ゴドーを待っていた二人に少年から「行く」という手紙が届く。ベケットの作ではゴドーは、結局来ない。しかしゴドーは、二人現れ両者自分こそほんものだと主張する。おもちゃ会社ではついに新作ゲーム『ソウル・ライフ』ができたことが報告される。そのゲームは、インターネットによって「今」に常時接続されるようになったことで、現代人が失ったノスタルジーの復活を目指すものだった。そして『ソウル・ライフ』は社長の娘みよ子を救うために一か月前から作られ、みよ子の生活のデータが入力されている。それを知らなかった部長は、憤りを露にする。社長が部長を問い詰めると、部長がアイデアを売ろうとしていたことが判明する。しかし社長もうまくいかなかった場合は、計画倒産を画策していることを部長に指摘され、全員「ゴドーは来ないんだね」と絶望する。次の瞬間、研究員が『ソウル・ライフ』に続く、新商品を開発した云って皆騒ぎだす。そこにまた少年が現れ、「みよ子はどうでもいいのか」「人が人を救わなくてもいいのか」と言う。四人はゴドーの世界に急激に移り、無意味な世界の「不安」からの「救い」について叫び、弾け飛んで「神が存在しないなら、神を発明しなければならない」といい、放心する。そこに、医者に扮した少年、Eが現れ、四人は精神障害を持った犯罪者であることを観客に告げてくる。それもまた芝居であって、Eは次の医者の役がDであることを知らせるが、ABCは認めない。Eが「ストップ」というと争う四人は止まり、これは最新のテクノロジーで映像化された一人の女性のイメージであるとまた言い出す。Eは、自分たちがその女性を治療するためにありとあらゆる手段を取ろうとしてきたと言うセリフの途中で、四人はEを止める。四人は、私が責めるべきは私自身である、私に残されたのは、例えばみよ子の遺書と述べて、最後の手紙を読む。私は『ソウル・ライフ』で決して自分を傷つけない他者に囲まれた生活を送っていた、しかしたった一人のソウル・メイトとも出会わないだろう、ユートピアなんて、真理なんて、初めから存在しないとわかっていながら、私は真理を、神様を探そうとしている。私は『ソウル・ライフ』を止めて、生まれ変わりを信じ、孤独を受け入れることにしたと四人は宣言する。最後は冒頭と同じ音楽、同じ群唱、その最後のセリフは「ぼくはひとり」。
鴻上尚史(1958-)
愛媛県生れ。早稲田大学法学部卒業。在学中に劇団「第三舞台」を結成。1987年「朝日のような夕日をつれて'87」で紀伊國屋演劇賞を受賞し、1994年「スナフキンの手紙」第39回岸田國士戯曲賞を受賞。50年代生れ、70年代後半から本格的に活動しはじめた、第三世代の代表的存在である。
ノート
「劇団第三舞台が初めて紀伊国屋ホールに〝進出〟し、連日超満員の客を集めた公園、鴻上尚史作・演出『朝日のような夕日をつれて』も、少なくとも私の周囲の反応では、相当評価が分かれた舞台だった」(扇田昭彦『現代演劇の航海』リプロポート、1988年、377頁)
※扇田昭彦が書いているのは紀伊国屋ホールでの1985年上演について
本作は、1981年の旗揚げ作品。執筆当時、作者は22歳。「リュービック・キューブ」とベケット『ゴトーを待ちながら』が重要な契機となっている。渡辺えり子『ゲゲゲのげ』がそうだったように、人物と呼び名が着脱可能なものとして扱われている。渡辺では「呼ばれたその瞬間から」という意識だったが、本作では居場所が変わると、呼び名が変わるという意識で戯曲が書かれている。学生運動が終わると正義を論ずることは諦められ、嘲笑の対象となった。そして、若者がやっとの思いで手に入れた車では、松任谷由実が流れ、固定観念のなかの幸福へと妥協する。本格的な消費社会へと移行するなかで、「理想を追う」という意識の残滓が、若者を自分探しへと走らせる。その受け皿の一つとなったのはオウム真理教であったり、小劇場ブームであったのではないか。経済的には豊かであったから、若者のエネルギーは余りあっただろう。戦争でナショナリズムが陥落し、学生運動で共産主義も衰退したことで、日本人は政治をきっぱり諦めた。それでお金大好き国民になっていくわけだが、それもバブルで崩壊する。以降、経済的豊かささえ保証されなくなった平成・令和生れの若者は、エネルギーも限られているので、コスパよく配分することに躍起になっている。
「おもちゃ」というのが、とてもよい小道具として機能しているのかもしれない。それは人類の歴史において、かなり長い期間、つねに必要とされる道具であるから、普遍性がある。それでも外側は変わり続けるし、それによって友達や家族との関係も見て取れたりする。中心にもってくる小道具はこの作品をもって、重要である、といえるのかもしれない。「おもちゃ」というギミックがなくならない限り、愛され続けるだろう。なお、「再演」といっても中身はそれぞれで異なるようである。今一つ一つの公演について確認していくことはしないが、もしかすると、この戯曲の演出の変遷と戯曲の改変を追ってくと、1980年代以降の演劇の外形的変遷(照明や音響の技術的発展など)の一端が見えてくるかもしれない。
書籍には、まえがきとあとがきの様々なバージョンが収められていて、いい構成だと思った。帯にあるように、「変わらない。そして、変わり続ける戯曲」である。この戯曲は私が観劇した経験がある。京都大学の吉田寮食堂といで、改装前だったか、夏休み中のものすごい暑さのなかで、第三劇場の先輩を含めた俳優たちが着るスーツは、ついさっき水揚げしたワカメみたいになっていて、動くたびに汗が観客に飛んできた。まだほとんど演劇について何も知らない状態で、これが演劇というやつかと感じたのをよく覚えている。2014年版では、スマホ・アプリとか、オキュラス・リフトとかが出てくるが、そのような形で、戯曲の再演を通じて、過去と現在が出会う場所になっているというのは、作者自身が書いている通りの「幸福」である。