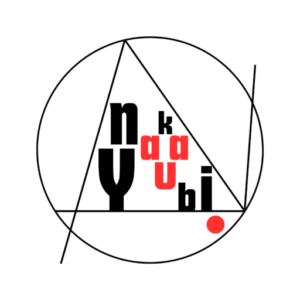【戯曲を読む】No.8 渡辺えり子「ゲゲゲのげ」1983年 岸田國士戯曲賞受賞
渡辺えり子 (2) ゲゲゲのげ/瞼の女 (ハヤカワ演劇文庫 19)
あらすじ
病床の老女を囲む四人の女。女は夢うつつの会話のなか最後に「マ・・・キ・・・オ」と言って、
源二と千太の場面に移る。二人は地面を調べている。また場面が移り、都会の小さな小学校。廊下で給食を食べるような、いじめられっ子のマキオのもとに、鬼太郎が現れる。鬼太郎が登場すると、生徒たちが河童に姿を変える。そして河童たちは「学校はもう河の底さ。今はもう河童の生徒が通ってる」と言う。すると学校は崩れ落ち、そこは林の中になっていた。マキオは自分がまぼろしの学校にもう半年もひとりで通っていたことを知る。マキオたちは、妖怪退治に出かけ、消えていく。真中が教壇に現れると、教室が林になっているのに気がつき、彼らもまた消える。千太と源二が目覚め、お盆をもったおかっぱ頭の少女と出会い、出されたコーヒーを喫する。しかしその少女は、子供に取り付く山の妖怪山童(やまんぼ)だった。源二は捕まるが、千太は鬼太郎を探しに逃げ延びる。源二はそのまま金縛りになってしまう。沢田研二の新曲とともに、茶の間でテレビを見ているマキオのもとには二人の母が入れ替わりに登場する。一方は、沢田研二を父と言い張る日出代で、もう一方は砂かけ婆である。後者のほうがカレーライスをつくりに台所へ去り、マキオがひとりになったところに、押し入れから声が聞こえてくる。声の主の女の子は冒頭の、病気の老女である。女の子は名前を付けないとそちらの世界にいけないと云うので、マキオは生まれる前に死んだ姉の一葉という名をつけた。カレーライス持って登場した母(砂かけ婆)と、銭湯から帰ってきた母(日出代)が鉢合わせする。二人の母が牽制しあっているところに、鬼太郎が現れる。砂かけ婆は正体が露見すると、今度は耳なし豚に変身する。追いつめられるマキオたちであったが、ぬり壁の助けが入り、耳なし豚を倒す。鬼太郎は、千太が呼んでいるを察知する。千太は、ねずみ男に追い詰められていた。鬼太郎が現れると、ねずみ男は態度を軟化させ、事情を聞いて源二を助けに行くことになる。いったんもめんがやられるが、鬼太郎が何かを念じ、山童を倒す。鬼太郎は消える。卒塔婆にバスが到着し、ねずみ男が降りる。生徒たちとともにバスに乗ってその場を去る。また林の中になり、そこでは鬼太郎がブランコをこいでいる。マキオが左足を鬼太郎の額の傷口に当てると、その渦の中に二人は消え入る。また教室に戻ってくる。転校生として千太が現れる。マキオはまた、廊下で給食を食べている。教室がまた林に変わり、青年の名で鬼太郎がまた現れる。「この俺達の歴史そのものが、この地球の、大いなる地球のただのセツナの夢に過ぎない事が判るときが来ても、俺はお前を許したりしない」などとと鬼太郎は言う。そこにマキオの姿をした一葉が登場する。元居たマキオの首を青年として現れた鬼太郎がしめながら歌う。中年の男がブランコを漕いでいる場面に移る。その中年の男はマキオであった。千太がビワの実を差し出しても、中年の男は黙ったまま、「永遠の夕方を凝視する」。「カラスが三度、オケラが四度、かすかに鳴いた」。最後に、冒頭のベッドの中の女の頬がかすかに光り、少し話すと「風が吹き、永遠の夕方が、かすかに笑った。ギーッ、バタン!」というト書きで幕。
渡辺えり(1955-)
※2007年までは渡辺えり子
山形県生れ。1980年から劇団3〇〇で活動し、70年代後半ごろから活躍した「第三世代」の代表的存在のうちのひとり。「第三世代」には野田秀樹、鴻上尚史、如月小春などがいる。
ノート
幾重もの物語が織り交ぜられ、多層的な独特の、一つの演劇空間を目指している。それを可能にしているのは、小劇場演劇のもつ圧倒的な統一力である。つまり、無数の物語を用意する=演劇の統一力に抗うことが、かえって演劇の強さを顕現させているものと思われる。同時代の思想的には「ポストモダン」の隆盛期でもあるから、明らかに時代の感覚とも連動している。表面的には、井上ひさしやつかこうへいの開いた境地と、テレビの影響を色濃く受け、それらは無意識のうちに連続しているものと思われる。「第三〇〇」というのは、お笑いやプロレスなどでも使われた。もっといえば、文学の世界にも「第三の新人」が先にあり、政治・経済の世界にも「第三世界」というものがある。「第三」、という言い方は、三好十郎『冒した者』(1952)にもあって、この時にはすでに膾炙していただろう。どこが本尊なのか確かめようがない。冷戦の只中、二項対立からの脱出に世界があがく煽りを受けた言い回しである。
ト書き、展開をはじめ、あまりに詩的で、散文的な勢いは、作者が述懐している通り、劇団あっての作品であることからくるものと思われる。本作をどのように上演するかは、作・演出・出演を兼ねる作者本人によってあらかじめ決められたイメージのうちにある。そのイメージを現実的上演たらしめているのは、劇団とその出演者たちであるわけであるが、さらにそれを支えているのはやはり経済成長期の日本であったかと思う。現在の若手にこれを実行するエネルギーはない。やはり演劇は興業としての要素を色濃くもつわけだから、戯曲も強い時代の制約を受けるということを如実にこの作が示している。
私が、渡辺えりを、井上ひさしを祖とした「物量演劇」セレクションに加えたのはこの戯曲を読んだからである。この戯曲の場合は、「最近の若いの」にはわからない固有名詞が多数登場する。「ゲゲゲのげ」というくらいだから、鬼太郎はもちろんのこと、ねずみ男、ぬり壁も出てくる(許可とったのかよ)。沢田研二の新曲という不親切なト書きもある(註に曲名が書いてあるが)。たまに、劇作家同士の話で、固有名詞を書いてもいいものかどうか、という話題になる。そして、結局程度の問題になったり、作品によるというところに落ち着くのだが、読む側としてはこれだけふんだんに散りばめられていることに対して、見出すものがあってもいいと思う。私は少なくとも、それが意識的だろうと、無意識的だろうと「抽象化」されていない状況に、上演当時の雰囲気を感じ取る。今や、たとえ同じ若者といっても同じものを見ているとは限らないばかりか、没交渉という状況なので、固有名詞つまり、「具体的な言葉」の取り扱いには注意が必要である。しかし当時は、2024年現在よりは、トレンドをシェアできた時代だったと想像できる。だから、それほど「固有名詞」の取り扱いが問題になりにくい、という側面もあったのかもしれない。あるいは、わからなくてもそう簡単に調べることもできない。観客は、目の前で起きていることそれ自体を、信用し、集中するしかなかったのかもしれない。