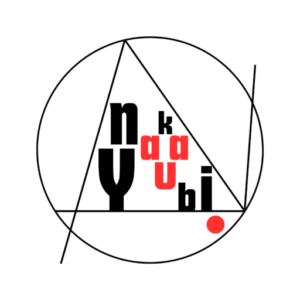【戯曲を読む】No.7 井上ひさし「藪原検校」 発表/初演:1973年
あらすじ
語り手の盲太夫が語り始める、藪原検校の物語。
彼は、元小悪党の父七兵衛と醜女といわれる母お志保のあいだに生れる。七兵衛は子が盲人であることがわかると、子育ての金を得るために座頭を殺した因果と悟り、自害してしまう。母が懸命に育てた子は、やがて琴の市のもとに預けられ、「杉の市」と名乗る。杉の市は若い時分から金にも女にも手癖が悪く、その手は師匠の女房お市にまで及ぶ。しかし杉の市は、声がよく、何処へ行っても大盛況になるため見逃されていた。ある日杉の市が早物語でおひねりをもらっていると、佐久間検校が結解を連れ立って、いちゃもんをつけてくる。佐久間に食って掛かる杉の市に、結解は匕首を抜いて仕置きをしようとする。しかし、杉の市は匕首を抜いて返討。杉の市は大騒ぎの舞台から、母お志保のもとに逃げ帰る。ところが母はまさに売春しようとしているところであった。杉の市は、現れた客の男とも喧嘩になるが、止めようとする母を誤って殺害してしまう。舞台での騒ぎのせいで、師匠は佐久間にお金を差し出さねばならなくなっていた。その金を見繕うために、琴の市は女房との関係を利用して、弟子の闇討ちを企てる。しかし、お市は逆に夫の胸を一突き。最後の力をふりしぼって夫も女房を殺害して、相討ちに終わる。杉の市は、五十両の金をもって阿武隈川を渡って江戸へと逃れる。その道中、杉の市は七転八倒している老人と出会う。その老人の金ほしさに、鍼を打つといってまた殺人。錆びた身幅の広い短刀を手に入れる。到着した日本橋の宿で、刀の錆落としを刀砥ぎ師の善兵衛に依頼する。そこで塙保己市という勾当の名を聞く。善兵衛は、錆刀が「庖丁透かし正宗」という名刀であることを見抜き、杉の市を問い詰める。即座に、杉の市は善兵衛を刺殺する。
江戸での暮らしも板につきはじめ、様子の変わった杉の市。殺しの前歴がわからぬように「酉の市」と改名していた。酉の市は、塙保己市に挨拶と出会う。両者の意見はかみ合わず、師弟になるべきではないという点だけが一致する。そして、「酉の市」は人格円満なる一代目藪原検校のもとで平曲を学びつつ、高利貸付で頭角を現していた。七、八年後、懐の温まった一代目の殺害を企てる杉の市。その密談の最中、女が一人現れる。その女はかつて殺害したはずのお市だった。杉の市は、お市を大川に突き落とす。そしてついに、一代目藪原検校を殺害し、まんまと二代目藪原検校の座についた。襲名披露で議論する杉の市とと保己市。金に執着する杉の市と、学問に執着する保己市とでは、やはり意見は合わない。再びお市が現れる。大川に突き落とされたあともやはり彼女は生き延びていた。杉の市は正宗を抜こうとするも中々抜けない。気がつけば、人だかりができており、杉の市は、金を渡すから人殺しをしようとする、罪について見逃してほしいと人々に懇願する。ここで悪運が尽きて二代目藪原は、盲、輪者は倹約されるべき存在と、みせしめに縛り上げられ、首を斬られる。幕が下り始め、最後に盲太夫の悲痛な声。「藪原検校 行年二十八」。
井上ひさし(1934-2010)
山形県に生れ。上智大学仏語科を卒業後、放送作家として活動する。1964年4月から放映された国民的人気番組『ひょっこりひょうたん島』を手掛ける。1969年『日本人のへそ』で一躍劇作家として認知させた。1983年に自身の作を上演する、こまつ座を立ち上げ。また長きにわたって、岸田國士戯曲賞の選考委員を務めた。そのほかの作として、『十一ぴきのネコ』『國語元年』(1986)、『父と暮せば』(1994)、『化粧』(2000)などがある。
ノート――世はまさに大物量時代
戦争は知らない
作家本人のイメージと、作品のイメージとは、経験上、一致することのほうが多い。岡田利規はまさに『三月の五日間』のああいう感じだし、太田省吾、別役実、井上ひさしも残っている音声や映像を見る限り、「ほんとにこんな人なんだ」という印象がある。井上ひさしはかなり露骨なほうで、例えば本作のこの部分、
結解はまた琴の市を殴ろうとする。そのとき、
盲太夫 註の六。
ト、註釈を入れるので結解の右の拳は琴の市の左頬の直前で停止。
盲太夫 これが佐久間検校の十八番。この男、(・・・・・・)
(中略)
結解は改めて琴の市を殴ろうとする、ところへ、
盲太夫 註の六の補足イ。
結解はもうちょっとのところで動作を停止しなければならなくなる。
盲太夫 ま、佐久間検校の語る平曲や浄瑠璃が、座頭たちよりはるかに上手ならば、一里うんぬんの作法も、座頭たちには我慢ができる。むしろ(・・・・・・)
井上ひさし『藪原検校』(『井上ひさし 全芝居 その一』所収、新潮社、1984年、597頁)
は、この盲太夫に井上ひさしの影を感じとることができる。例えば、平田オリザと井上ひさしの対談のなかでは、話し出すと本人ですら止められないという雰囲気が記録されている。
・・・(略)・・・統一にはひとつの世界観がいるので仏教もまた漢字とともに伝来してくる。こちらからも本場の中国大陸へ出かける留学僧などもふえる。・・・・・・大筋だけを話しているつもりですが、長くなってすみません(笑)。
井上ひさし・平田オリザ『話し言葉の日本語』小学館、2003年、240頁。
平田 どうぞ、どうぞ。
井上 漢字が十分に入ってきたころ、中国大陸は長い内乱時代を迎える。そこで、日本は大陸とのつきあいをやめてしまいます。こうして・・・・・・・
扇田昭彦は、「『藪原検校』はじつにおもしろい舞台だった。おそらくは唐十郎作・演出の『ベンガルの虎』(状況劇場)と並んで、一九七三年を代表する舞台のひとつになることは間違いない」(『現代演劇の航海』所収、1988年、103~104頁)と書いているが、本作と、井上ひさしという作家の登場は、1973年を象徴すると言ってもいいのかもしれない。
いわゆる新劇に分類されるような戯曲を読んだあとに井上ひさしを読むと、ようやく演劇も「カラーテレビ」の時代に入ったなという印象を受ける。なぜかといえば、戯曲のなかの情報量の膨大になるからである。われわれ後追い組は、戦後日本史をメディアを通じて知っていくときに、荒廃した国土の白黒の映像と玉音放送のラジオという敗戦描写にはじまり、学生運動があり、1970年の三島由紀夫の自決の白黒画面を通過すると、1970年の大阪万博を色付きで三波春夫『世界の国からこんにちは』が流れ、「明るい時代がはじまる」というのが前半のお決まりのパターンである。戦後間もない時期に入った時点で、カラーで撮影された日本の写真は存在しているので、どうしても戦時下は白黒にしておきたいというメディア側の演出的意思(あるいは無意識)が働いているのかもしれない。とはいえ、数値から見ると、1973年は高度経済成長の膨張の極致にあり、同年にカラーテレビの普及率が白黒テレビを超えたらしい。2000年代から2010年代も、スマートフォンの普及で、恐らく人が一日、あるいは通勤通学の30分で手にする情報量が飛躍的に増えたわけだが、当時との違いは情報量も物量もともに増えたという点だろう。物量時代の到来である。
私は、野田秀樹、松尾スズキ、渡辺えり、鴻上尚史あたりの演劇を、おおざっぱに「物量演劇」と括っている。不快に言えば「バブル・浪費演劇」である。この始祖とでも言うべき存在が井上ひさしである。ただ、井上ひさしの場合はまだインテリや文学の香りが色濃く残っていて、ここで引用したような知識のひけらかしがある。それが「知識のひけらかし」みたいに見えないようにできるかどうかが、現代の若者に向けた演出では試されるところなのかもしれない。なお、これに対応する「清貧演劇」も脈々と受け継がれていて、別役実、太田省吾、平田オリザの流れもある。
そんなやつはいない
井上ひさしの戯曲を読むときには、徹底的に「そこが舞台である」という意識のもと、戯曲を読んでいかなければならない。これより前に書かれた戯曲だと、例えば『表裏源内蛙合戦』は、平賀源内を、表の源内と裏の源内という二つの登場人物に分離させて、その葛藤を表現したり、『道元の冒険』は現代の精神病患者として治療を受けている男の夢のなかという趣向があったりする。そして、これらは、舞台がわからない人を置き去りにするというものではなく、こんな楽しそうなことが行われているのなら、劇場に行ってみたいな、という気持ちにさせるだけの魅力がある。
また、戯曲のなかにこれだけ音楽をばらまかれると、「戯曲を読む」という行為は挫折しかける。なんとかついていけないかと思ってみると、別役実も『藪原検校』について書いていた。とにかく「多様で多彩な感触を持つ作風はない」ということを読んで、ひとまず安心する。これ以上はそうそうないということだからである。二代目の藪原検校は存在しておらず、まったくのフィクションらしい。このことに、別役はショックを受けた(別役実『ことばの創りかた――現代演劇ひろい文』論創社、2012年、24頁)。ショックを受けたのは彼一人ではなく、専門の学者も「二代目がいたなんて知らなかった」と後で手紙を出したりしたとのこと。
何を狙っているかと言いますと、学者や研究者の方々が書いていらっしゃること、それらあらゆる資料、そういったものをすべてあたっても、ここだけはわからないというところを探し出すのが真の目的です。
井上ひさし・平田オリザ『話し言葉の日本語』小学館、2003年、194頁。
「学者や研究者では、できないことをやる」。こうした姿勢は、「書いていらっしゃる」と尊敬語ではあるが、「反近代」的ともとれる。そして、『藪原検校』にいたるまでに何作も「評伝劇」を書いてきたので、何も知らずに観劇したら、「そんなやつもいたのかなあ」という気分になる。ところが、「そんなやつはいない」らしい。井上ひさしが恐るべき分量の文献にあたっていたということは周知の事実であるが、そうやって書いていきながら「突然、中心を抜いてみたらどうなるだろう」と思うことで、逆に作劇の手法が明らかになるのかもしれない。しかし、この手法を明らかにするためには、少なくとも井上ひさしが確認した文献と同じ量の文献にあたらなければならなくなる。ここも、論証性・妥当性を究める場ではないし、それは演出家や俳優の仕事には含まれていない。別役のテキストがやや混乱しているように見受けられるのは、『藪原検校』のために井上があたった資料を確認していないからかもしれない。もちろん、仕方のないことである。ただ、以下の発言からわれわれは、別の視野からまた考えることができるかもしれないので、この戯曲をそのうち手に取ってみようと思う。
平田 井上さんに、資料をまったく使わないなんていう作品もあるんですか。
井上ひさし・平田オリザ『話し言葉の日本語』小学館、2003年、195頁。
井上 あります。『国語事件殺人辞典』、『花子さん』・・・・・・、だいぶ失敗してますね(笑)。資料を使わずに成功したのは、『日本人のへそ』、『化粧』、『雨』、『きらめく星座』、『雪やこんこん』ぐらいでしょうか。