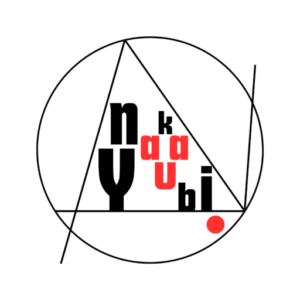【雑記】別役実を見て、鈴木忠志を読む――2025年1月18日
ときどき無性に、戯曲を声に出して読みたくなることがある。それは発作的なもので、毎週戯曲研究会をやっていた頃の後遺症のようなものなのかもしれない。
最近やっと、京都で倉庫にしまっていた本を広げて、1960年代から1970年代の戯曲を読み始めた。谷崎からはじめてようやく半世紀が経過したところである。井上ひさし、別役実の戯曲を読むと、グッと現代日本演劇のことばに近づく雰囲気がある。今私が思う、「演劇っぽい」ことばというのは、ここからはじまったのかということが見えつつある。別役実も、井上ひさしも、いずれも「クソおもんない上演」が初見だったので、長らくイメージが悪かった。以降も、コンクールで別役実『受付』が課題戯曲に含まれていて、たまたま持っていてコロナ禍のなかでわざわざ貸してくれた後輩には申し訳ないが、これを読んで駄作だと断じ、谷崎を選んだり、『組曲虐殺』を借りたが結局積読になってしまったり、ご縁がなかった。
しかし、この二人が日本の劇作史上ものすごく重要であることは勉強をしなくてもひしひしと感じられる。今、いちばんえらいポジションにいる人たちは、岸田國士戯曲賞で「お選びいただいた」りしているので、故人となっていることも相まって半ば、神格化されているような印象がある。「実体験」というのは恐ろしい。何も知らない自分は幸運である。
私を演出家にしたのは、この戯曲『AとBと一人の女』である。
ただ、この一文を読んで、何かの示唆を自分与えるのかもしれないと思い直した。劇作を外枠から考え直すことにつながるだろうということで、戯曲の演出をしはじめたのだが、演出のときの考え方と劇作のときの考え方が、大きく乖離してしまい、作・演を兼ねるという一般的に最も経済的な手段が、自分にとっては最も困難なそれになってしまい、困り果てている。別役実の作品のイメージと、鈴木忠志の作品のイメージは驚くほどかけ離れている。それでも事実として、それも自覚付きで、二人のはじまりが同じだったということは、無知な自分にとっては驚嘆に値する。鈴木忠志の原点に、文楽があるということは(著名な著作二、三をパラパラとめくった限りではほとんど主だった言及がない)、人から聞いたり、『日経新聞』の「私の履歴書」で明白になっている。「父方の祖父が空襲で焼けた東京を逃れ、我が家にやってきた。竹本綱寿太夫を名乗る義太夫語りだった。三味線とともに、ものすごい声を家中に響かせる」。当人がいうように、「身体の記憶は歳月をへて私の演劇に立ち現れてくる」。これは彼の作品のイメージと一致する。歌舞伎と浄瑠璃は、相互に影響を与え合いながら、発展した歴史がある。身体表現の歴史のなかに〈人形〉が深く入り込むという点に、日本の演劇の特徴があって(それは今、漫画・アニメと2.5次元舞台の関係に、無意識のうちに引き継がれている)、無理くり欧米的なスタイルを取り込もうとした「新劇」に、まったをかけた鈴木忠志が持ってきた文脈は「新劇という近代を撃つために「前近代」を持ってくるやり方」(太田省吾)であり、そこに父方の祖父の義太夫語りと三味線が含まれていないはずがない。
それにしても、結局、何がどう転がって、鈴木忠志が別役実とともに創作をし始めたのか、まったく意味がわからない。別役のその後については、鈴木忠志だけでなく、参加したコンペティションで審査員を務めておられた笠松泰洋や、扇田昭彦など、いろいろな人が全員同じようなことを言っていて、これだけわかりやすい段階を踏んでいったのなら、わざわざ全作読まなくてもいいのではないかなどと考えている。ただし、意味がわからないということは、何かとても重要な点が隠されている、ということなのかもしれない。今、ほかにやるべきことはもちろんたくさんあるのだが、せっかく得た余暇なのでなるべく好きなことをやっておきたい。はやく20世紀の演劇を修了したい。