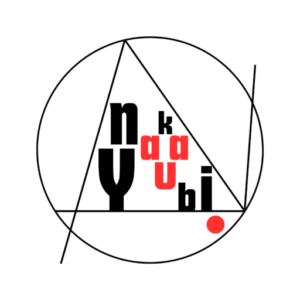【戯曲を読む】No.4 三島由紀夫『サド侯爵夫人』 発表/初演:1965年
あらすじ
母と再会し、サン・フォン伯爵夫人のいびりを華麗にはねのけるサド侯爵夫人ルネは、現在逃亡中の良人サド侯爵アルフォンスを救ってほしいと母に懇願する。しかし、母モントルイユは、ルネの妹アンヌとアルフォンスのあいだに肉体関係があったことを知るや否や、アルフォンスの処遇について、三通の手紙を送る(第一幕)。第一幕より六年後。ルネは、アルフォンス釈放の知らせを受けて、喜びに溢れる。しかしルネは妹と、良人の真の愛情がどちらに向かっているかについて口論になってしまう。さらには、サン・フォン伯爵夫人は、モントルイユが六年前、自身を利用して、判決破棄に尽力しながらも、すぐあとで破棄を断ったことを蒸し返す。今度は再審がなされた直後に、王家の裁判権で投獄されると踏んでいたということまで暴露される。結局アルフォンスは、ヴァンセンヌの牢獄に、それも前より劣悪な環境の独房に移っている。娘の仕合せを想ってアルフォンスと別れさせたい母モントルイユと、アルフォンスとの共に生きることこそ自分の仕合せであると頑として譲らない娘とのあいだで、激しい言い争いになる(第二幕)。第二幕から十三年、フランス革命の直後、モントルイユが信じていたかつての正義や法は無力化していた。ルネは、アルフォンスが自身をもとに描いた物語「ジュスティーヌ」を読み、そのなかにかつての自分たちの世界が閉じ込められてしまった、それは人のなせる業じゃない、アルフォンスのなかには人の心はもうない、と悟り、出家を決意したと云う。すでに決心は固く、シャルロットからサド侯爵が現れたと聞いても、十九年にわたって待ちに待ったはずのアルフォンスを拒絶する。(第三幕)。
三島由紀夫(1925-1970)
1949年、小説『仮面の告白』で大きな成功を収め、戦後派の作家として活躍。ノーベル賞候補に上るなど、日本の枠を超えて高く評価される。戯曲も新劇系を中心に多くの演出家によって上演され、現在にいたるまで根強い人気を誇る。1960年代頃から、民兵組織「楯の会」を結成するなど政治活動に傾倒するようになり、1970年11月、自衛隊市ヶ谷駐屯地(現在の防衛省)へ乱入し、かけつけた自衛隊員らにクーデターを呼びかけ、そののち割腹自殺した。代表作に、長編小説『金閣寺』(1956)、戯曲『鹿鳴館』(1956)、短編小説『憂国』(1961)など。
ノート
女性のみが登場する本作は、男性のみが登場する『わが友ヒットラー』と対になる作品。本作において三島は、イプセン、チェーホフらのように、西洋の自然主義の戯曲の持病である矛盾、舞台の細部にわたってわれわれの住む現実世界ありのままでありながら、退屈でないもの=劇的なものを描かなくてはならないという問題をかなり簡単な方法で解決している。その方法とは、ほとんどの者が共感できなさそうな異常者アルフォンスを舞台の外部に配置することで、すべての登場人物の行動を、自然であるいは「共感可能な」存在として、駆動させるという方法である。つまり三島は、それがたとえ本人のものであっても、捉えようのない感情の始原を劇の外側に追いやることで、三島らしい整理整頓された簡潔明快で窮められた論理性をセリフに顕現させているのである。(参考:別役実『ことばの創りかた』、ゴードン・ファレル(常田景子訳)『現代戯曲の設計』)