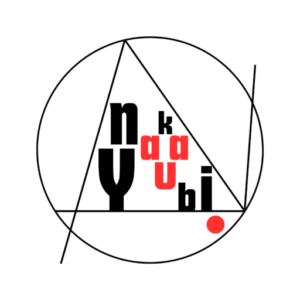【戯曲を読む】No.3 木下順二 『夕鶴』 発表/初演:1949年
木下順二 『夕鶴』(新潮文庫版)
木下順二『夕鶴』(新装版、未来社)←神田が読んだほうはこっち
あらすじ
一面の雪のなかにぽつんとある一軒の小さなあばらや。子どもたちのわらべ唄で開幕。子どもたちは、つうと遊びたがっているが、与ひょうが現れる。与ひょうは、女房のつうが織る美しい布でひと儲けしていた。それを聞きつけた惣どと運ずは、家に忍び込み、機屋などを物色する。つうに見つかり、二人は取り繕おうとするが、つうとは意思の疎通が図れない。その様子を見、惣どと運ずはつうが人間ではなく鶴ではないかと訝しがる。惣どと運ずは、与ひょうにまた布を織らせ、都で高く売ろうと働きかける。食事の折、与ひょうはつうにまた布を織ってほしいと要求する。つうは金欲に溺れる与ひょうを嘆くが、離れないで済むならと与ひょうの要求を受け入れる。惣どと運ずは、覗いてはならぬと言われている機屋の様子を覗き、そこにはつうではなく鶴がいた。二人が去ったあと、与ひょうも機屋を見てしまう。二枚も布を織ったために、やせ細って現れたつうは、与ひょうが約束を破ってしまったために、つうは去らねばならなくなったという。一枚は大切にとっておくよう与ひょうに言い残して、つうは鶴になって消える。残された布を摑んだまま与ひょうは立ちすくむ。つうとよく遊んだ子供たちのわらべ唄が流れて来て幕。
木下順二(1914-2006)
戦後派の作家。旧東京帝国大学大学院英文科修了。作品はプロレタリア系出身の民藝などでしばしば上演される。晩年は東京都名誉都民を辞退するなど国家的名誉を受けず、左翼としての筋を貫いた。そのほかの代表作に民話劇『彦市ばなし』(1943年)や、『平家物語』をもとに書かれた『子午線の祀り』(1978)がある。英文学者中野好夫のもとで学び、シェイクスピアの翻訳の仕事もある。
ノート
私欲にまみれた者たちと、鶴であるために「おかね」の概念が理解できないつうが対比されている。本作には、アメリカ的資本主義は欲望に身を任せるばかりで、人間存在にとって重大な物事を見えにくくするという左派ならではの現代社会への批評的視野が含まれている。また、木下による『子午線の祀り』に至るまでの古典への姿勢は、新劇の系譜による日本の古典へのアプローチの集約点とされる(参考:西堂行人(日本演出者協会編)『演出家の仕事 六十年代・アングラ・演劇革命』れんが書房新社、2006年)。
個人的には、戯曲の思想が説教くさくてあまり好きではない。ただし、木下順二の著作を読み、別の視点からの関心が湧いてきた。
いろんな地方のことばの中からおもしろい効果的なことばを拾って来て、自分の感覚によってそれらを組み合わせまぜ合わせたということになりますが、最初は自然にそうであったものがだんだん意識的になり、そしてこのせりふの書きかたを少々立体的に使ってみたのが『夕鶴』(一九四九年)ということになりましょうか。三人の男たちが使うこの種類のことばとつうという女性の使う別なことば(これを自分では〝純粋日本語〟と呼んでいるのですが)とによって、彼らと彼女の持つ世界の共通性と違いとを、そしてやがて二つの世界の断絶を表現してみようとしたわけです。
木下順二『戯曲の日本語 日本語の世界12』中央公論社、1972年、271頁。
私は、自分の持っている数少ない武器の一つである、関西弁をここ二作でか、「標準語」とぶつからせてきた。方言(木下順二は地域語と呼ぶが)は、話し言葉を書く劇作家にとって、重要なトピックである。劇作家協会の交流会などでも、かなり頻繁に話題に上がる。木下順二は同書を、家庭の事情で東京から熊本に引っ越したときに苦労したことを述懐するところからはじめている。自分にはそのような経験はないのだが、小学生の頃に東京から転居してきた友人が似たような体験をしたことをしばしば聞いた。現代では、軋轢はやや弱まっているように感じられるが、言葉の違いがあるものを嘲笑の対象とする文化は、根強く残っているだろう。対東京ということになった場合、関西弁はやや恵まれた環境にあるというか、コンプレックスを持つというより、もはや「誇り」としてあくまで維持するという人も多くいる。もちろん、これはたぶん、大人になってからという緩い条件付きで、多勢に無勢になりがちな幼少期だと、当人には巨大な問題としてのしかかることになる。しかし、こうした素朴な言語体験は、小説で言うところでの「原風景」として劇作家たちの鋭敏で、独特な言語感覚を持たせるのかもしれない。だから、自分もいま一つ、大事にしてみようと思うことにした。
ただ、対東京弁(標準語)という単線的なところでしか闘えないというのは少し心もとないような気もする。それは、中央集権的な状況を認めてしまうことにつながりはしないかと思う。京都弁を少し学んでみはしたが、つかみ切るというところにまでは至れなかった。いくつか用意されている道がある。そのうち二つは明確なような気がしていて、別役実のように独自の文体を打ち立てること、井上ひさしのように怒涛の量を学ぶことである。この二人はかなり対照的に見える。両者とも、あまりに作品点数が多く、取り組もうと思うとため息が出るが、彼らの時代より圧倒的に情報を収集しやすい時代に生まれたアドバンテージを、もっと有難がらねばならない。