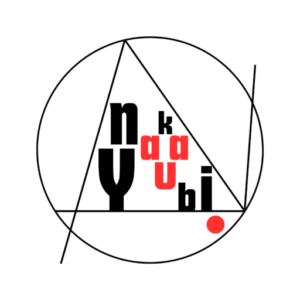【戯曲を読む】No.1 野上彌生子『腐れかけた家』 発表:1927(昭和2)年
野上彌生子『腐れかけた家』 (所収:野上彌生子全小説 〈15〉 戯曲)
あらすじ
東北の地主塚本圭一の家。塚本家は、村役場と小学校の改築の財源確保のため、村の功労者である先代が植えた並樹を伐採する話を止められないほどに没落していた。妻の竜子はそんな家の凋落と田舎暮らしを厭い、東京に帰りたがってはヒステリーを起こし、病みつきがちな日々を過ごしていた。ある日圭一が竜子の従弟である牧田喬と偶然汽車で再開し、家に連れてくる。喬は自身の縁談を纏めるため、帰郷する途中だったのだが、しばらく塚本の家の厄介になる。そこで、喬は圭一のの妹、芳子に惚れてしまう(第一幕)。しかし芳子は兄圭一を憂い、牧田とともに塚本家を出ることを拒む。二週間後、竜子が牧田に自分を東京へ連れて帰るようにせがみ出す。牧田は断るが、竜子は出て行ってしまう。牧田は竜子を追う(第二幕)。しかし、豪雨で汽車は脱線し、竜子と牧田はその日の夜に帰ってくる。雨音が家を激しく打つなか、小学校も潰れかけ、圭一は補修に乗り出そうとする。竜子は、今にも朽ち果てそうな塚本家から自分は抜け出せないという運命を悟り、圭一も牧田と芳子がともに東京へ行くことを促すのであった(第三幕)。
野上彌生子(1885-1985)
明治女学校卒。夏目漱石に師事し、初期は私小説から出発。『青鞜』に参加し、中期にかけて、自分の印象に残った出来事に取材し、そこに社会性を加えた作品に変化していく。やがて文壇の最長老となり、99歳で没するまで作品を発表し続けた。野上は、ロシア文学者の湯浅芳子に宮本百合子を紹介し、百合子と芳子はのちに共同生活を送る。
ノート
チェーホフ『桜の園』で描かれる貴族の没落を、野上が夫豊一郎と講演旅行に出かけ、そののち十和田湖畔に家族で暮らした経験とかけあわせたものらしい。芳子は当時訪ねた友人の工藤哲子がモデルと推測される。「「腐れかけた家」は、東北の地主が主人公となっている。地主塚本恵一は妻竜子、妹芳子と山や田畑や古い家屋敷の残る田舎で暮らしている。しかし昔の繁栄はなく、家計は傾きかけ家は半分腐りかかっていた。という設定である」(亀井美由紀『野上弥生子論』1995年、111頁)。解題を開いてみると、野上彌生子の『日記』にこのような記述があるとのこと。孫引きで恐縮であるが、「チェホフ。桜の園を読みながら工藤家のことがふと頭に浮かんだ。またロシヤの地主階級が崩壊すべき種子はすでに久しく蒔きつけられてゐたことをつく〴〵と感じさせられる。彼等の堕落、精神的のたいはいと向上心の欠乏――生きる力の弱さは、ちょうど江戸末期の所謂旦那様連を思はせる」(宇田健「解題」のうちの引用部分『野上彌生子全小説〈15〉戯曲』、445頁)。孫引きで留めたのは、野上彌生子の偉大さに私がたじろいだという、情けない事情による。どこかの機会で正面から向き合いたい。
東京から地方に移住した人と、旅行で来る人の意見の相違など、地方と都会の暮らしの隔たりについて語られる、社会性を大いに含んだ戯曲といえる。発表は昭和2年で、岸田國士が批判した「戯曲時代」に近いのだが、劇作家として野上彌生子の名前が挙がることはあまり多くない。私自身、かなり前『桜の園』を下敷きにした『京の園』を書くために、同じように『桜の園』を下敷きにした戯曲を探すということがなければ、本作に出会うことがなかっただろう。『桜の園』では、「桜の園」が競売という「人間の営み」によって奪われるという結末である一方で、本作では豪雨という「自然現象」によって人物の企てが阻まれる。ここに、不条理を与えるものとして捉える日本の自然観と、征服の対象として捉える西洋の自然観のコントラストを見ることができる。
経験上、いろいろな場で、この戯曲を紹介すると関心を持ってもらえることがよくあった。それはもちろん、この戯曲に魅力があるからにほかならないのだが、検索をかけても上演歴はあまり出てこない。この記事をきっかけに上演される日が来るなら願ったり叶ったりである。